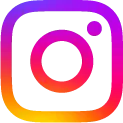ご飯を食べている時や飲み物を飲んでいる時に、急にむせることはありませんか?
あるいは、ポロポロと食べこぼすことが多くなったようなことはありませんか?
年齢を重ねるとあちこちの筋力が低下してくるように、お口周りも同じです。
本日はそんなお口周りの老化「オーラルフレイル」についてのお話です。※フレイルとは一言でいうと機能低下のことです。
このブログがお口周りの衰えが気になる方、まだそれに気がついておられない方の参考になれば嬉しいです。
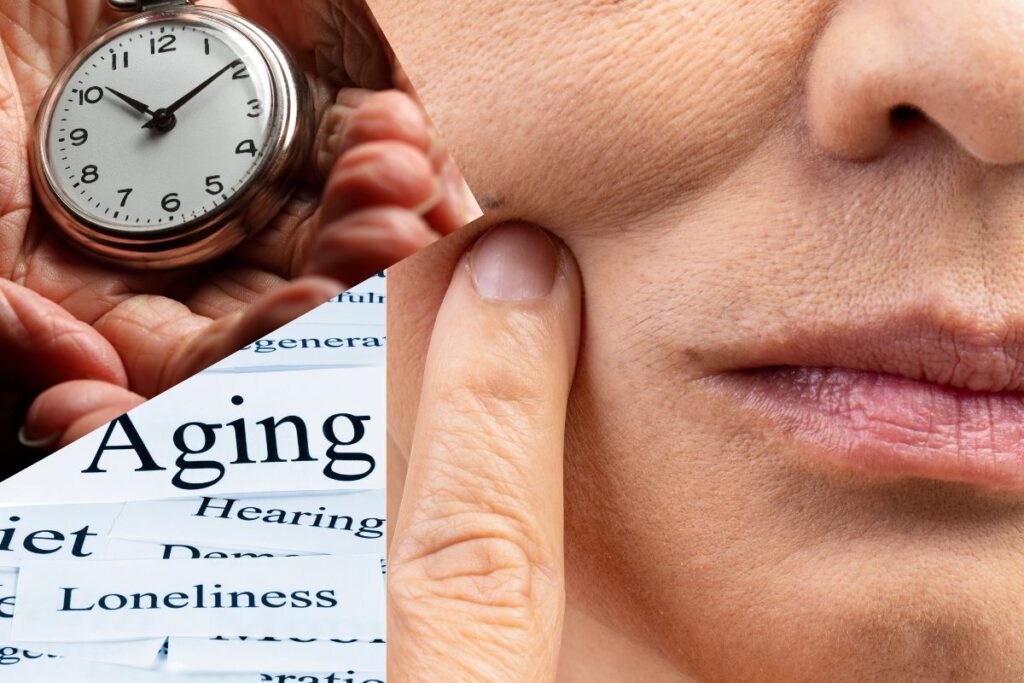
目次
実は口の機能低下「オーラルフレイル」は40代から始まると言われています・・・
まずはお口周りの老化度チェックです。
□自分の歯が20本以下(インプラント、差し歯は自分の歯とは数えない)
□硬い物が苦手になってきた
□噛むのが疲れる
□食事中やなんでもない時にむせることがある
□口の渇きが気になる
□滑舌が悪くなったと感じる時がある
□食べこぼすことが多くなってきた
□食べるのが遅くなった
□食べ物が口の中に残りやすくなってきた
いかがでしょうか?思い当たることはありますか?
一般的にこれらの項目の内、思い当たることが2つ以上あればオーラルフレイルが始まっているといわれます。
これらの症状は、ちょっとした変化から始まり、自覚しにくいことも多いため見過ごされがちです。
しかし、まだ大丈夫とオーラルフレイルを放置すると、気が付いた時には食事がうまく飲み込めなくなってしまうことにより、食事が十分に摂れなくなり、栄養状態が悪化したり、人との会話が億劫になるななどで、社会参加の機会が減るなど、最終的には全身のフレイルや生活の質の低下に繋がる可能性があります。
また、かつては高齢者の問題と見られがちだったオーラルフレイルですが、近年の日本歯科医学会・日本老年歯科医学会や民間企業、日本の複数の自治体や地域で行われた大規模な住民健診などの研究や調査で、より若い世代、特に40代からその兆候が現れ始めることが明らかになってきています。
過去に「歯と口の健康週間」などに合わせて、全国の40代〜60代の男女を対象としたオーラルフレイルに関する意識調査や実態調査した結果では40代でも約3割がオーラルフレイルの疑いがあるとも報告されています。
そのため、早期にこれらのオーラルフレイルの兆候に気づき、適切な対策を講じることが非常に重要だとされています。
日常生活に少し取り入れるだけで口の機能の維持・向上に役立つオーラルフレイル対策!
ここでは日常生活で手軽に取り入れられるオーラルフレイル対策をお伝えします。
パタカラ体操
パタカラ体操は多くの歯科医師や歯科衛生士、医療機関、介護施設、そして行政機関によって推奨されています。 口腔機能の維持・向上を目指す上で、非常に効果的で基本的な体操として広く認知されています。
- 「パ」:唇をしっかり閉じて破裂させるように発音します。唇の力、閉鎖力を鍛えます。
- 「タ」:舌を上の前歯の裏につけて離すように発音します。舌の先を動かす力を鍛えます。
- 「カ」:舌の奥を上げて発音します。舌の奥を動かす力、飲み込みに必要な力を鍛えます。
- 「ラ」:舌を丸めて発音します。舌を滑らかに動かす力を鍛えます。
- それぞれを大きく、はっきりと、連続して10回程度繰り返します。1日3セット程度行うのがおすすめです。
舌回し体操
- 口を閉じたまま、舌で歯茎をなぞるように大きくゆっくりと回します。右回し、左回しをそれぞれ10回程度行います。唾液腺も刺激され、唾液の分泌促進にもつながります。
- ほうれい線あたりを内からの押し出すようにするとほうれい線予防にもなります。
よく噛んで食べる習慣
食事は、口の機能を維持・向上させる最も自然なトレーニングです。
- 一口30回を目安に噛む: 意識的にゆっくりと、よく噛んで食べるようにしましょう。
- 様々な食材を食べる: 柔らかいものばかりでなく、適度に歯ごたえのある食材(根菜類、きのこ類、イカ、タコなど)も取り入れることで、咀嚼筋をバランス良く使えます。
- 左右均等に噛む: 片側ばかりで噛む癖がある人は、意識して両側で噛むようにしましょう。
唾液腺マッサージ
口の乾燥を感じる人におすすめです。唾液の分泌を促します。
- 耳下腺(じかせん)マッサージ: 耳たぶの下あたりを指で優しく円を描くようにマッサージします。
- 顎下腺(がくかせん)マッサージ: 顎の骨の内側、耳の下から顎の先に向かって指で優しく押しながらマッサージします。
- 舌下腺(ぜっかせん)マッサージ: 顎の真下、舌の付け根あたりを両手の親指で下から押し上げるようにマッサージします。
- それぞれ10回程度、食前や口が乾くと感じた時に行うと効果的です。
高速ブクブクうがい
口の周りの筋肉を効率よく鍛えることができます。
- 少量の水(30ml程度)を口に含み、口を閉じたまま、頬の筋肉と舌を使って高速でブクブクと音を立ててうがいをします。
- 水を口の中で前、上、下、左右に強くぶつけるように、できるだけ速く動かすのがポイントです。
- 最低7秒間に10回を目安に、起床時や毎回の歯磨きの後、飲食後などに行うと良いでしょう。
食事内容の見直しと工夫
- バランスの取れた食事:
- 特定の栄養素に偏らず、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂ることが重要です。特に、口周りの筋肉や全身の筋肉を維持するためには、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)をしっかり摂ることを意識しましょう。
- 食物繊維の摂取:
- 野菜やきのこ、海藻類など、食物繊維が豊富な食材は、よく噛む必要があるため、自然と咀嚼力を鍛えることができます。
- 食事形態の工夫:
- もし、硬いものが食べにくいと感じる場合は、無理に硬いものを食べる必要はありません。食材を小さく切る、柔らかく煮込む、とろみをつけるなど、工夫することで、安全に、そして美味しく食べ続けることができます。ただし、柔らかいものばかりにならないように、適度に歯ごたえのあるものも取り入れる意識は持ちましょう。
- 少量頻回食:
- 一度にたくさん食べられない場合は、食事の回数を増やし、少量ずつ頻繁に栄養を補給することも有効です。
姿勢の意識
- 正しい姿勢での食事:
- 背筋を伸ばし、顎を少し引いた姿勢で食事をすることで、誤嚥のリスクを減らし、スムーズな嚥下を助けます。前かがみになりすぎたり、仰け反ったりしないように注意しましょう。
- 日中の姿勢:
- 普段から良い姿勢を意識することは、全身の筋肉、ひいては口腔周囲筋の維持にも繋がります。
発声・会話の機会を増やす
- 積極的に会話する:
- 人との会話は、口の筋肉や舌を自然と動かすことになり、滑舌の維持・向上に役立ちます。電話をする、友人と会う、家族と話すなど、意識的に会話の機会を増やしましょう。
- カラオケや音読:
- 声を出すことは、喉や口の筋肉を鍛える良い運動になります。カラオケで歌ったり、新聞や本を声に出して読んだりするのも効果的です。
適切な水分補給
- こまめな水分補給:
- 口の乾燥は、咀嚼や嚥下を困難にするだけでなく、虫歯や歯周病のリスクも高めます。意識してこまめに水分を摂りましょう。
- 特に、カフェインを含む飲料(コーヒー、緑茶など)やアルコールは利尿作用があるため、摂りすぎに注意し、水やお茶(ノンカフェイン)を積極的に摂るのがおすすめです。
口腔内ケアの徹底
- 歯磨きの徹底:
- 毎食後の歯磨きはもちろん、フロスや歯間ブラシを併用して、歯と歯の間や歯周ポケットの汚れもしっかり除去しましょう。
- 入れ歯の手入れ:
- 入れ歯を使用している場合は、毎日清掃し、清潔に保つことが重要です。合わない入れ歯は、咀嚼能力を低下させるだけでなく、口内炎などの原因にもなるため、定期的に歯科医院で調整してもらいましょう。
定期的な歯科受診
- 虫歯や歯周病のチェック、入れ歯やブリッジの調整、クリーニングなど、プロによる定期的なケアは、口の健康を保つ上で不可欠です。
- 歯科医師や歯科衛生士に、オーラルフレイルについて相談し、個別の指導を受けることもできます。
禁煙・節酒
- 喫煙: 口腔内の血流を悪化させ、歯周病を悪化させる最大の要因の一つです。口腔機能の維持のためにも禁煙が強く推奨されます。
- 過度な飲酒: 口腔内を乾燥させたり、栄養状態に影響を与えたりする可能性があります。
これらの対策は、どれか一つだけをやるのではなく、複数を組み合わせて継続することが大切です。ご自身の生活習慣や口腔の状態に合わせて、無理なく取り入れられるものから始めてみてくださいね。
よく笑う人はオーラルフレイルになりにくい!!
福島県立医科大学医学部疫学講座の研究グループによると、笑うこととオーラルフレイルの間には、非常に密接な関係があり、よく笑う人はオーラルフレイルになりにくいという結果が発表されています。
具体的には、「ほとんど笑わない人」を基準とした場合、「ほぼ毎日笑う人」のオーラルフレイル発症リスクは、約62%低いという結果が示されました。
笑いの頻度だけでなく、毎日会話をする人のオーラルフレイルリスクも約58%低いことや、抑うつ症状がない人のオーラルフレイルリスクも低いことが示されており、笑いや社会的交流、精神的な健康が口腔機能に良い影響を与えることが多角的に裏付けられています。
笑うことがオーラルフレイル予防に繋がる理由
主な理由は以下の通りです。
- 口腔周囲筋の活性化
- 笑うとき、私たちは顔の表情筋や口の周りの筋肉、そして舌の筋肉を大きく動かしています。特に、大声で笑う際には、口角を上げたり、頬を引き上げたり、顎を動かしたりと、普段の会話よりも多くの筋肉を使います。
- これらの筋肉は、咀嚼(噛むこと)や嚥下(飲み込むこと)、そして発話(話すこと)といった口腔機能に直接関わっています。笑うことでこれらの筋肉が活性化され、衰えの予防・改善に繋がると考えられます。これは、口腔機能の「筋トレ」のような効果があると言えるでしょう。
- 唾液分泌の促進
- 笑うことは、リラックス効果をもたらし、自律神経の中でも副交感神経を優位にします。副交感神経は唾液の分泌を促す働きがあるため、笑うことで唾液が出やすくなると考えられます。
- 唾液は、食べ物の消化を助けるだけでなく、口の中を洗い流して清潔に保ち、細菌の増殖を抑え、虫歯や歯周病を予防する重要な役割を担っています。唾液の分泌が低下すると口が乾燥し、オーラルフレイルの症状の一つである「口腔乾燥」を引き起こしやすくなるため、唾液分泌の促進は非常に有効な対策です。
- ストレス軽減と精神的な健康の維持
- 笑うことは、ストレスホルモンを減少させ、気分を向上させる効果があることが知られています。
- ストレスや抑うつ状態は、全身のフレイルだけでなく、口腔機能の低下にも関連することが示唆されています。精神的に健康な状態を保つことは、食欲の維持や人との交流意欲にも繋がり、結果として口を使う機会を増やすことにも繋がります。
- 社会交流の促進
- 笑いは、人と人とのコミュニケーションを円滑にする重要な要素です。よく笑う人は、自然と社会的な交流が増える傾向にあります。
- 社会的な交流が増えれば、会話の機会も増え、口を動かす頻度も高まります。これも、口腔機能の維持に貢献すると考えられます。
「笑う門には福来る」ということわざは、まさにオーラルフレイルの予防にも通じる、科学的な真実を含んでいます。
日々の生活の中で、意識的に笑顔を増やしたり、笑う機会を作ることを心がけるのが大切ですね。
そうだったのか?!私の食べこぼし・・・
とても恥ずかしいお話ですが、実は私はここ最近になって、自分の食べこぼしが気になっていました。
汁物などを口にする直前にこぼしてしまったり、気が付けば洋服にシミが出来ていたりすることもあります。
ごくごくたま~~~にですが、何~~~~にもない時に、自分の唾が気管に入ってむせることがあります。
こういう時ってめちゃくちゃしんどいんですよね~~~。息が出来なくなって・・・・。
動画を撮っていても滑舌が悪いな~~~~と思うこともしょっちゅうですし・・・。
最初のチェックに照らし合わせると、かなりオーラルフレイルが進行してきている・・・と判断できます・・・・。・・・かなりまずい状態ですかねぇ~~~・・・・
私は毎朝、化粧をする前に耳下腺、舌下腺あたりのマッサージは欠かさずやっておりますし、大口を開けて笑うことは得意、サンゴくん歯磨きで口腔ケアもバッチリやってはいるんですが・・・。
前述の対策のうち、「よく噛んで食べる」の項目など出来ていないこともあるんですよね。
つまり、何か対策を一つや二つをやってもダメで、出来ることをちょくちょく総合的にやっておくことが大切なのかなと思います。
一部は全体を表し、全体は一部を表す
東洋医学には、人体全体が小宇宙であり、その小宇宙の一部である耳や手もまた、その小宇宙(人体)全体の情報を反映している。という考え方があります。
簡単にいうと、「体の一部は体全体を表し、体全体は体の一部を表す。」という考え方です。
このような考え方からいえるのは、口の機能が弱ってきているということは、体全体の機能も弱ってきているということです。
つまり、私を含め、オーラルフレイルの前兆の心当たりがある方は、全身の健康のために今すぐ何らかの対策を始めないといけないということになります。
いつもとちょっと違う。何にかがおかしい。に気が付くことが大切
繰り返しになりますが、オーラルフレイルの兆候といわれている症状は、ちょっとした変化から始まり、自覚しにくいことも多いため、見過ごされがちです。
私自身も、このブログを書きながら期せずして自分自身がオーラルフレイルの兆候があることに気が付いてしまいました。
まさか、食べこぼしがオーラルフレイルに繋がるとは・・・。
今日、いえ、今すぐにパタカラ体操を始めます。
みな様もお口周りに関することで「アレ、以前はこんなことなかったのに・・」「あれ、なんか以前と違う・・・」このように感じられることがあれば、オーラルフレイルが始まりつつあるかもしれません。
ぜひ、普段生活を送られるにあたり、チェック表を思い出していただき、思い当たることがないかをチェックしてみてください。
そして思い当たることが一つでもあった場合は、お口のみならず、全身の健康に気をつかい、できる対策を少しずつ始められることをお勧めします。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入りさえすればどんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。
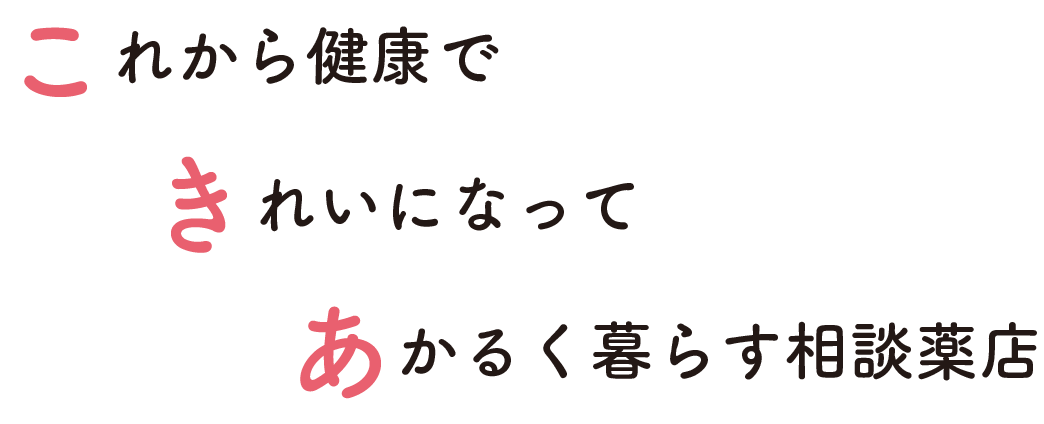

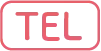 06-7897-7116
06-7897-7116