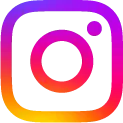真夏が過ぎ、しかしまだまだ残暑が厳しい9月。
みんな夏の疲れが溜まってきている頃ですね。この連休はひたすら朝寝坊・・・なんて方もおられるのではないでしょうか。
本日のブログでは、休日が近づくと「今度の休みは寝るぞ~~!!」と思われる方に、寝だめの仕方についてお話します。
少し過ぎてしまいましたが、9月3日は、「グッ(9)スリ(3)」の語呂合わせで、「秋の睡眠の日」とされています。
このブログが「ぐっすり眠りたい!」「寝ることで夏の疲れを取りたい、英気を養いたい!」と思われておられる方の参考になれば幸いです。

目次
平日と休日の生活リズムのズレは、まるで海外旅行後の時差ぼけ
いつもは仕事や学校で規則正しい生活を送っているのに、休日前の夜になると突如として訪れる解放感!
そして、ついつい夜更かしをして、休日は遅くまで寝てしまう……そんな経験、ありませんか?
私はあります。
休日前夜、ついつい韓流ドラマをもう1話、もう1話・・・と気がつけばけっこうな時間になってしまっている・・・💦
そして休日の朝はいつもより2時間ほど朝寝坊をして、のんびり起きて・・・
そして、その晩、なかなか寝付けなくなる・・・・・(アカンやんか~~~~い)
私に限らず多くの方が「平日頑張ったご褒美」として休日に朝寝坊をして生活リズムを崩しがちですが、実はその行動が、知らず知らずのうちに私たちの体と心に大きな負担をかけているようなのです。
寝だめはソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)を引き起こす
一般的には「寝だめ」とは、平日に不足した睡眠を補うために、週末や休日などにいつもより長く寝る行為です。
この「いつもより長く寝る」という行為が、具体的には休日の起床時間を平日の起床時間より大幅に遅らせることを意味する場合がほとんどです。
つまり、平日と休日の生活のリズムがずれてしまうということですね。
この、平日と休日の生活リズムのズレは、まるで海外旅行後の時差ぼけのように、私たちの体内時計を狂わせてしまいます。これを「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」といいます。
私たちの体には約24時間周期の「体内時計」が備わっており、睡眠、覚醒、体温、ホルモン分泌、血圧など、体の基本的な機能をコントロールしています。
そしてその体内時計は朝、光を浴びることでリセットされ、規則正しい生活によって正常に機能します。
ところが週末に遅くまで寝ることで、朝日の光を浴びるタイミングが遅れ、体内時計が後ろにずれてしまいます。
ずれた体内時計のまま休日明けに平日の起床時間に戻すと、体は時差ぼけ状態となり、眠気、だるさ、集中力低下といった症状が現れます。
休み明けに体がだるかったり、やる気が全く起こらない経験がある方も多いのではないでしょうか。
また、睡眠時間が不規則になることで、睡眠の質が低下する可能性があります。その結果、十分に休まった感覚が得られず、かえってだるさや疲労感が残ることもあります。
睡眠リズムが乱れると、食事の時間も不規則になりがちです。また、日中の体を動かす時間が減ったりしてかえって心身のストレスが増えたりすることも考えられます。
要するに朝寝坊は体のリズムを狂わせてしまい、あまり健康には良くない・・・・という事のようです。
睡眠不足の放置より寝だめ(キャッチアップ睡眠)をした方がまだマシ
ところが、いくつかの研究では、平日(労働日)に睡眠時間が不足している人が、週末に十分な睡眠をとる(いわゆる寝だめをする)ことで、死亡リスクや心血管疾患(心臓病や脳卒中など)の発症リスクが低下する可能性が示されています。
- 中国・南京医科大学の研究(2023年): 平日の睡眠時間が6時間未満の集団において、週末の寝だめが2時間以上であると、心血管疾患発生のリスクが低下したと報告されています。(Sleep Health誌)
- スウェーデン・ストックホルム大学の研究(2018年): 平日の睡眠時間が短くても、週末に朝寝坊していた人の死亡率は、常に7時間睡眠を確保していた人と変わらなかった、という結果が示されました。ただし、これは65歳未満の層で顕著でした。
これらの研究は、「寝だめが直接的にどれほど有益か」という点についてはまだ議論の余地があるものの、「平日の睡眠不足を放置するよりは、週末に多少なりとも補う方が良い」という可能性を示唆しています。
また、高齢者を対象とした研究では、週末の寝だめ(キャッチアップ睡眠)が認知機能障害のリスクを低下させる可能性を示唆する報告もあります。
- 台湾・National Taiwan Normal Universityの研究(2024年): 高齢者を対象とした研究で、週末のキャッチアップ睡眠が認知機能障害リスクを70%以上低下させる可能性が示唆されました。(Sleep Breath誌)
以前は「寝だめは体内時計を狂わせるだけ」という側面が強調されがちでした。しかし、近年では以下のような視点も加わり、より多角的に評価されるようになっています。
- 「睡眠負債の返済」という側面: 完全に帳消しにはできなくても、蓄積した睡眠負債を一部でも返済することで、心身への悪影響を軽減する効果があると考えられています。
- 「何もしないよりはマシ」という現実的なアプローチ: 現代社会では、平日に推奨される睡眠時間を毎日確保するのが難しい人も少なくありません。そうした状況下で、週末の睡眠で少しでも不足分を補うことの意義が見直されています。
とはいえ、決して不規則な生活をお勧めしている訳ではありません。
基本毎日規則正しく、十分な睡眠時間を確保することが基本ですが、あくまでも、諸事情によりそれが叶わない方に限り、寝だめはしないよりマシということになります。
生理機能の調整は睡眠中央値が鍵を握る!
睡眠中央値という言葉はご存知でしょうか?
「睡眠中央値」とは、寝ている時間帯のちょうど真ん中の時刻を指します。
例えば、深夜0時に寝て朝8時に起きた場合、睡眠時間は8時間です。この睡眠時間の中央値は、午前4時となります。
私たちの体には、約24時間のサイクルで動く体内時計が備わっています。この体内時計は、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部分にあり、光(特に朝日の光)によってリセットされ、体の様々な生理機能、すなわち体温、ホルモン分泌、睡眠・覚醒リズムなどを調節しています。
睡眠中央値は、この体内時計がどの時間にセットされているかを示す重要な指標です。
例えば、夜中に急行列車が走っていると想像してみてください。この列車が毎日同じ時刻に同じ駅の中間地点を通過することで、駅(体)の周りの他の活動(ホルモン分泌、体温変化など)も、その時刻に合わせて正確に動きます。
- 寝る時刻(入眠時刻): 電車の「出発時刻」のようなものです。
- 起きる時刻(覚醒時刻): 電車の「到着時刻」のようなものです。
- 睡眠時間: 電車が走っている「時間」です。
出発時刻や到着時刻、走っている時間が多少前後しても、「運行の中間地点」が毎日大きくずれないことが、その路線の全体的な安定運行には最も重要です。
これと同じように、睡眠中央値が毎日安定していることが、体内時計全体の安定には最も大切なのです。
したがって睡眠中央値が毎日大きく変動すると、体内時計が乱れやすくなってしまいます。
体内時計を極力狂わさない寝だめの方法
平日と週末で睡眠中央値が大きくずれることを、前述のように「社会的ジェットラグ(Social Jetlag)」と呼びます。
これは、あたかも飛行機で時差のある国に行ったかのような状態が毎週起こっていることを意味します。
社会的ジェットラグが大きいほど、肥満や糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病のリスクが高まるという研究結果が報告されています。
理想は、平日も週末も睡眠中央値が大きくずれないようにすることです。週末の寝だめによって睡眠中央値が大幅にずれる場合は、そのずれを小さくすることを意識すればよいということになります。
具体的には、
睡眠中央値のずれを最小限に: 平日と週末で、睡眠の中間時刻(睡眠中央値)が2時間以上ずれないように意識すること。
「早寝・早起き」よりも「早寝・遅起き」: 平日に不足した睡眠を補うために週末に少し長く寝る場合でも、無理に普段より早く寝るのではなく、普段より遅く起きることで睡眠中央値のずれを抑える工夫も有効です。
具体的には、いつもは午後12時に寝て午前6時に起きる人の場合、睡眠中央値は午前3時、それが2時間寝だめをするために、休日に午後12時に寝て午前8時に起きると、睡眠中央値は午前4時。その差は1時間。同じく4時間寝だめをするために、午後12時に寝て午前10時に起きると、睡眠中央値は午前5時。その差は2時間。ギリ2時間です。
もう少し寝だめの時間が欲しい場合は、午後11時に寝て午前10時に起きると11時間睡眠で睡眠中央値は午前4時半。普段との差は1時間半となります。
かといって普段12時に寝ている人が、寝だめをするためかつ、睡眠中央値をずらさないために、休日前にだけ午後10時に寝て午前9時に起きる。(睡眠中央値は午前3時半)・・・これは現実的でしょうか。
よほど疲れている時には12時を待たずに眠ってしまうこともあるでしょうが、あまり現実的でなないように思います。
結論。休日に寝だめをする場合、普段より気持ち早めに寝て、普段より2~3時間の寝坊をするのが最も体内時計への影響が少ない。というようなことになるでしょうか。
寝ても寝ても寝足りない・・・これはこれで問題あり。
睡眠というものは、人間の3大欲求のひとつです。
それくらい人間が生きていく上で重要なものである訳ですので、睡眠時間の確保が重要な反面、「睡眠中央値が!睡眠中央値がずれてしまう!!」と考えて睡眠をとることはそれ自体がストレスになってしまうような気がします。
寝たい時には寝る。
休日の朝には「あ~~~よく寝た!!」と、満足して起きる方がよほど健康的なように思います。
そして、もし、どれだけ寝だめをしてもすっきりと目覚めない、寝ても寝ても寝足りない・・・というような方の場合。
これは心身のどこかに問題があるように思います。
ふつう、人は十分睡眠がとれるとそれ以上は眠れなくなる仕組みで出来ています。
もし、寝ても寝ても寝足りないという場合、どこか心身の不調が隠れていないかを確認するためにも、一度専門家にご相談されるのもいいかもわかりません。もちろんこきあ相談薬もご相談をお受けします。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。
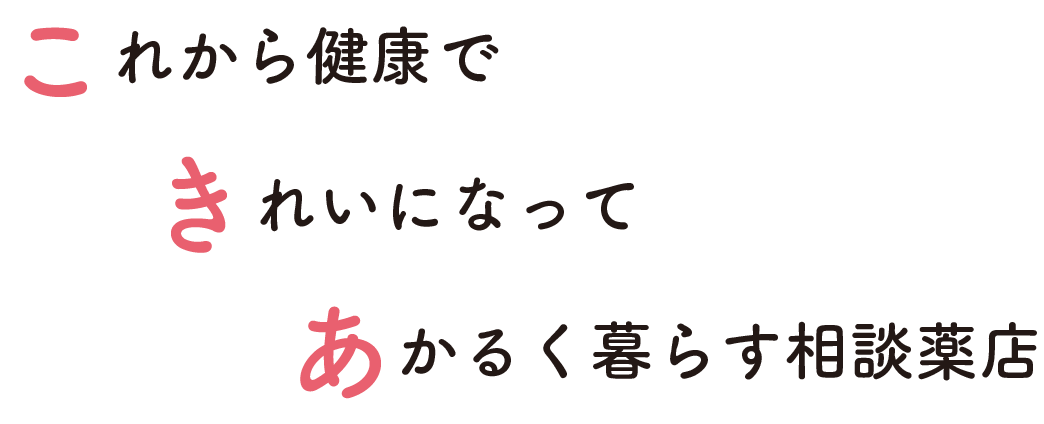

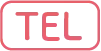 06-7897-7116
06-7897-7116