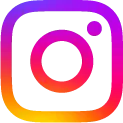夜中に突然起こる足のつりは、激しい痛みを伴うこともあり、恐怖そのものです。
よく用いられる芍薬甘草湯を枕元に置いておられる方もあるかもしれません。今回は、そんな恐怖の夜中に足がつる原因と対策について解説します。

目次
夜中に足がつる主なおもな5つの原因
ミネラルバランスの乱れ
筋肉の正常な収縮と弛緩には、カルシウム、マグネシウム、カリウムといったミネラルが不可欠です。これらのミネラルのバランスが崩れると、筋肉が過剰に興奮しやすくなり、つりを引き起こす可能性があります。
- カルシウム: 筋肉の収縮をスムーズに行うために重要です。 不足すると、筋肉が過敏になり、わずかな刺激でも収縮しやすくなります。
- マグネシウム: 筋肉の弛緩を助け、神経の興奮を鎮める働きがあります。不足すると、筋肉が収縮したままの状態になりやすく、けいれんを引き起こしやすくなります。また、カルシウムの吸収を助ける役割も担っています。
- カリウム: 細胞内外の水分バランスを調整し、神経や筋肉の機能を正常に保ちます。不足すると、筋肉の興奮性が高まり、つりやすくなります。
こんな方は要注意!
- 偏った食事をしている方(とくに高血圧予防で野菜中心の食生活を送っている方)
- ダイエット中で栄養バランスが崩れている方
- 激しい運動で大量に汗をかいた利した時
- 利尿作用のある飲み物(コーヒー、アルコールなど)をよく飲む方
- 骨粗鬆症予防でカルシウム製剤を摂取している方
ミネラルは食事からバランス良く摂取することが基本ですが、サプリメントで補う場合は、単一のミネラルだけでなく、天然のミネラルバランスに近いもの(例えば、海のもの由来のサプリメントなど)を選ばれることをお勧めします。
脱水
私たちの体の約60%は水分でできており、筋肉の働きにも水分は不可欠です。熱中症、入浴や運動による過剰な発汗などで体内の水分が不足し、血液がドロドロになると、筋肉への酸素や栄養の供給が滞ります。老廃物の排出も滞り、筋肉の疲労回復が遅れることがあります。夏場はもちろん、季節を問わずこまめな水分補給が重要です。
また、前述しましたように、発汗などによって水分とともに電解質(ナトリウム、カリウムなど)も失われ、ミネラルバランスが崩れることがあります。
寝ている間は水分補給ができないため、寝る前にコップ一杯の水を飲む習慣をつけると良いでしょう。また、日中もこまめに水分補給を心がけてください。
筋肉の疲労
長時間歩いたり、運動などで筋肉を使いすぎたりすると、体はそれを夜間に回復しようとしますが、その過程で筋肉が過敏になり、足がつることがあります。
- 長時間の立ち仕事やデスクワーク: 同じ体勢を続けることで、特定の筋肉に負担がかかり、疲労が蓄積します。
- 運動不足: 普段運動不足の人が急に激しい運動をすると、筋肉が対応できずに疲労しやすくなります。
- 合わない靴での歩行: 足に合わない靴を履いていると、特定の筋肉に負担がかかりやすくなります。
適度な休息やストレッチ、マッサージなどで、日中の筋肉の疲労を和らげることが大切です。
冷えと血行不良
寝ている間は体が冷えやすいので注意が必要です。
筋肉の硬直: 冷えによって筋肉が硬くなり、わずかな刺激でも収縮しやすくなります。夜間に足の筋肉への血行が悪くなると、栄養が行き渡らず、冷えも加わって足がつりやすくなります。
血行不良による酸素・栄養不足: 筋肉に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなり、筋肉の機能が低下します。
寝る前に湯船にゆっくり浸かる、温かい飲み物を飲む、靴下やレッグウォーマーを着用するなどして、体を温めるようにしましょう。
夜間低血糖
電解質バランスの急激な変動:
- 血糖値が急激に上昇すると、それを下げるためにインスリンが大量に分泌されます。インスリンは、血糖を細胞に取り込む際に、カリウムなどの電解質も細胞内に移動させる作用があります。
- 血糖値スパイク後の急激なインスリン分泌は、一時的な電解質バランスの変動、特に低カリウム血症を引き起こす可能性があります。カリウムは筋肉の正常な収縮と弛緩に不可欠なミネラルであり、不足すると筋肉が過敏になり、夜間の足のつりを誘発する可能性があります。
血管内皮機能の変化:
- 血糖値スパイクは、血管内皮細胞に一時的な負担を与え、血管の機能(拡張・収縮など)を低下させる可能性があります。
- 夜間に血流が悪化しやすい状況下で、血管内皮機能が低下していると、筋肉への酸素や栄養の供給が滞り、老廃物が蓄積しやすくなります。これが筋肉の異常な収縮、つまり足のつりを引き起こす可能性があります。
神経系の影響:
- 低血糖は、自律神経系に影響を与えることがあります。自律神経の乱れは、筋肉のコントロールにも影響を及ぼし、異常な筋肉の収縮を引き起こす可能性があります。
- 糖尿病による神経障害(糖尿病性神経障害)がある場合、低血糖がさらに神経の機能を不安定にし、足のつりを誘発する可能性も考えられます。
筋肉のエネルギー不足:
低血糖は、筋肉のエネルギー源であるブドウ糖が不足した状態です。筋肉がエネルギー不足に陥ると、正常な機能を維持できず、収縮異常が起こりやすくなる可能性があります。
閉経後の女性に足がつることが多くなる理由
女性ホルモンが低下する閉経後の女性は、様々な理由により血糖値が急激に変動しやすくなります。
- エストロゲンは、筋肉や肝臓などの細胞表面にあるインスリン受容体の数を増やしたり、その機能を高めたりする働きがあると考えられています。閉経によりエストロゲンが低下すると、インスリン受容体の感受性が鈍くなり、インスリンが正常に作用しにくくなります(インスリン抵抗性の増大)。そのため甘い物などを食べた時に急激に血糖値が上がりやすくなります。
- ホルモンバランスの変動に伴い自律神経も乱れやすくなります。自律神経は血糖値のコントロールにも関与しており、そのバランスが崩れると血糖値の急激な変動を招きやすくなります。
お風呂上がりの冷たい甘い物(特に異性化糖を使ったアイスクリーム、ヤクルト、かき氷など)を食べる習慣は、口腔内から糖が速やかに吸収されるため、急激な血糖値の上昇を引き起こしてしまい、その後、急激な血糖値の低下(夜間低血糖)を招き(=血糖値スパイク)、足の痙攣の原因となることがあります。
※異性化糖(いせいかとう)とは、主にトウモロコシやジャガイモ、サツマイモなどのデンプンを原料として作られる液状の糖のことで、デンプンを酵素で分解してブドウ糖にし、さらにその一部を別の酵素で、より甘味の強い果糖に異性化(構造を変化させること)して作られます。
砂糖に比べて安価に生産でき、使い勝手の良さから 清涼飲料水、炭酸飲料、果汁飲料、乳酸菌飲料、アイスクリーム、デザート類、ジャム、シロップ、調味料(タレ、ドレッシングなど)、パン、菓子類など、幅広い食品に利用されています。
そして白砂糖を使ったものに比べ、口腔内から速やかに吸収され、血糖値を急激に上げてしまいます。
足のつり対策をして恐怖の夜をなくしましょう!
季節や生活習慣に合わせていくつかの対策を試すことで、症状を軽減できる可能性があります。出来ることから対策をしていきましょう。
すぐにできる対策
- 寝る前のストレッチ:
- ふくらはぎをゆっくりと伸ばすストレッチ(壁に手をついて、片足を後ろに伸ばし、かかとを床につけたままキープ)を左右30秒程度行いましょう。
- 足首をゆっくりと回したり、上下に曲げ伸ばししたりするのも効果的です。
- アキレス腱を伸ばすストレッチも忘れずに。
- 水分補給: 寝る前にコップ一杯程度の水を飲む習慣をつけましょう。ただし、冷たすぎる水は身体をひやしてしまいますし、飲みすぎると夜中にトイレに行きたくなるので、適温適量を心がけてください。
- 体を温める:
- 湯船にゆっくり浸かる(38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分程度)。
- レッグウォーマーや靴下を着用して寝る。特に足首を温めるのが効果的です。
- 使い捨てカイロをふくらはぎに貼るのも良いですが、低温やけどには注意してください。
- 冬場は電気ごたつや湯たんぽを利用する。
- 寝具の見直し:
- 布団が重すぎると、足に負担がかかりやすくなります。軽い布団に変えてみるのも一つの方法です。
- 足元が冷えないように、毛布などを足元に一枚足すのも良いでしょう。
- マッサージ: 寝る前にふくらはぎや足の裏を優しくマッサージすることで、筋肉の緊張が和らぎ、血行が促進されます。マッサージオイルやクリームを使うとより効果的です。
日頃から意識したい対策
- ミネラルバランスの調整:
- カルシウム(乳製品、小魚、緑黄色野菜)、マグネシウム(ナッツ類、海藻類、緑黄色野菜)、カリウム(果物、野菜)などをバランス良く摂取しましょう。
- サプリメントで補う場合は、単一のミネラルではなく、天然のミネラルバランスに近いもの(例えば、海のもの由来のサプリメントなど)を選ぶようにしてください。
- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなどの適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強くする効果があります。ただし、激しい運動は逆効果になることもあるので注意が必要です。
- 同じ体勢を避ける: 長時間立ちっぱなしや座りっぱなしの作業は、筋肉疲労や血行不良の原因になります。適度に休憩を挟み、軽いストレッチや足踏みなどを行いましょう。
- 靴の見直し: 足に合った靴を選び、ヒールの高い靴や底の薄い靴は長時間履かないようにしましょう。
- 血糖コントロール: 血糖値スパイクを防ぐためには食事の時間や食事の内容、食事の摂り方などに注意が必要になります。以下のブログに詳しく書いてありますので、血糖値スパイクが気になる方はこちらをご覧ください。
日頃から特殊乳酸菌を飲むことも血糖値スパイクを防ぐことにつながります。
- 脱水予防: 日中もこまめに水分を摂取する習慣をつけましょう。特に運動後や入浴後はしっかりと水分補給をしてください。
医療機関への相談
これらの対策を試しても頻繁に足がつる場合や、痛みが強い場合は、念のため医療機関を受診することをおすすめします。特に、以下のような場合は早めに受診しましょう。
- 頻度が徐々に増えている
- 痛みが激しい、または長く続く
- 足のむくみや痺れを伴う
- 既往歴に糖尿病、腎臓病、甲状腺の病気などがある
医師に相談することで、大きな病気が隠れていないかを確かめることができます。
実は私も経験しています・・・
よくお姑さんが夜中に足がつって、それはそれは痛い!ということを言っていたのを、若いころは「ふ~~ん」という感じで聞いていたのが、数年前から夜、椅子に座ってテレビを観ている時や夜中に突然、足がつりそうになることがたまにあります。(もしくは、軽くつってる・・・?!)
つりそうになっただけでもその違和感、痛みといったら・・・あのまま本格的に足がつると、いったい痛みはどのようなものなんだろう・・・と、考えただけでも恐怖です。お姑さんの気持ちが今になってよくわかります。
最近はお風呂に入った時に湯船の中でふくらはぎをマッサージしたり、暖かくなってもレッグウォーマーをして寝たり、日々、海由来のミネラル補給を欠かさずしたりと、私も出来る対策をしています。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします
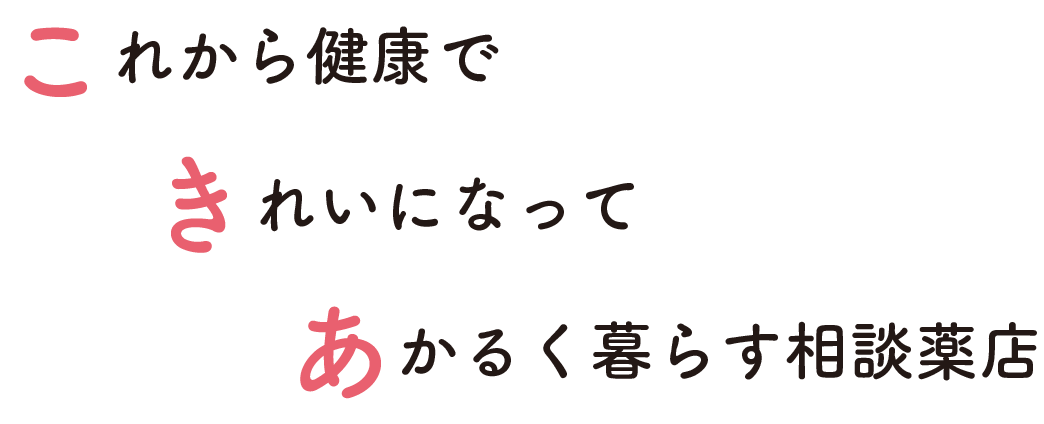

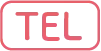 06-7897-7116
06-7897-7116