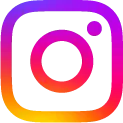「暑い!つらい!!」「暑い!!しんどい!!」と言って毎日を過ごすのと、「暑いのは暑い季節だからね~」と言って過ごすのとでは、果たしてどちらが心身には良いでしょう。
本日のブログでは、厳しい酷暑を乗り切るために、少しでも心身の消耗を少なくし、すこしでも快適に過ごすために、東洋医学的観点から先達が残してくれた知恵をご紹介します。
少しでも皆様のお役に立つことを願っています。
目次
①心身一如(しんしんいちにょ)
心と体は切っても切り離せないもの。体が健康なら心も安定しやすい。心が病めば体にも不調が出やすく、体が病めば心も落ち込みやすい。ということです。
たとえば、ストレス(心の問題)が胃の痛み(体の問題)として現れたり、風邪をひいて体がだるい時(体の問題)に気分まで憂鬱になったりするのは、まさに心身一如の考え方。
夏は、中医学でいう「心(しん)」の季節であり、陽気が最も旺盛になる時期です。しかし、この強い陽気(暑さ)が心身のバランスを崩しやすい要因にもなります。
夏の心身への影響
- 心(精神)への影響: 夏は「心」の季節です。心は精神活動を司るため、暑さや高ぶる陽気は、心に熱をこもらせやすくします。これにより、以下のような心の不調が現れやすくなります。
- イライラや焦燥感: 暑さによる不快感が、心の平穏を乱し、精神的な不安定さにつながります。
- 不眠や寝つきの悪さ: 体内にこもった熱が心を興奮させ、寝つきを悪くしたり、眠りが浅くなったりすることがあります。
- 集中力の低下: 暑さによる消耗と心の乱れが、思考力や集中力を低下させることがあります。
- 体(身体)への影響: 夏の暑さは、体にも様々な変化をもたらします。
- 汗による「陰液」の消耗: 汗をかくことで、体を潤す「陰液(いんえき)」が大量に失われます。これにより、体の乾燥(肌、喉)やほてり、寝汗といった「陰虚(いんきょ)」の状態になりやすくなります。
- 「気」の消耗と夏バテ: 暑い中で活動することで、体全体のエネルギーである「気」が消耗しやすくなります。これが夏バテのだるさ、倦怠感、食欲不振につながります。
- 消化機能の低下: 暑さで食欲が落ちたり、冷たいものの摂りすぎたりすることで、胃腸の機能(脾胃:ひい)が弱まり、消化不良や下痢を引き起こしやすくなります。
このように、夏は体(暑さ、汗、気や陰液の消耗)も心(イライラ、不眠、集中力低下)も両方に負担がかかりやすい時期です。だからこそ、「心身一如」の考え方を意識した養生が重要になります。
②心静自然涼(しんせいしぜんりょう)
夏に特に意識したいのが「心静自然涼(しんせいしぜんりょう)」です。
これは心が穏やかで静かであれば、必要以上に暑さを感じず、自然と体も涼しく感じる。という意味の心身一如(しんしんいちにょ)の考え方を体現した言葉になります。
ストレス、不安、イライラといった感情(心の状態)は、体内に「熱」を生じさせたり、気の巡りを滞らせて体温調節を乱したりすると、東洋医学では考えます。
例えば、イライラすると顔が赤くなったり、カーッと熱くなることがありますが、これは心が体に影響している典型的な例です。
イライラやストレスを溜めると、体内の熱がさらに高まり、心身の消耗を加速させます。瞑想、深呼吸、何もしないゆったりとした静かな時間を設けるなどが有効です。
③抑目静耳(よくもくせいじ)
さらに、心静自然涼(しんせいしぜんりょう)に役に立つのが、目と耳を使いすぎず、感覚器官を休ませ、心を穏やかに保つという意味の抑目静耳(よくもくせいじ)です。
- 抑目(よくもく): 目を抑える、つまり、テレビやスマホの画面を長時間見すぎない、細かな作業で目を酷使しない、まぶしい光を避け、目を休ませる。
- 静耳(せいじ): 耳を静かにする、つまり、騒がしい場所を避け、大音量で音楽を聴いたりせず、耳を休ませる。
現代社会においては、情報過多やデジタル機器の普及により、私たちは常に目や耳から多くの刺激を受けています。これが「過労」となり、心身に様々な不調をもたらすと考えられます。
- 目を使いすぎると「肝」を傷める: 肝は血を貯蔵し、気の巡りを司ります。目を酷使すると肝の血や陰液を消耗し、目の疲れ、かすみ、イライラ、不眠などにつながるとされます。
- 耳を使いすぎると「腎」を傷める: 腎は生命の根源的なエネルギーや潤いを司ります。大音量や騒音で耳を酷使すると腎の精気を消耗し、耳鳴り、難聴、足腰の弱り、老化の加速などにつながるとされます。
心の平穏を保つ: 目や耳から入る過剰な情報は、心を乱し、精神的なストレスを増大させます。心を穏やかに保つためには、五感への刺激を適度に抑えることが不可欠です。心が落ち着けば、体もリラックスし、自律神経のバランスも整いやすくなります。
④酸甘化陰(さんかんかいん)
「酸味(酸っぱいもの)と甘味(甘いもの)を組み合わせることで、体内の陰液(いんえき=体の潤い、体液、血など)を生成・補充する」という薬膳の法則。
- 酸味の役割: 酸味には「収斂(しゅうれん)作用」といって、引き締めたり、漏れ出るのを防いだりする働きがあります。汗のかきすぎを抑えたり、体内の潤いが逃げるのを防いだりする効果が期待できます。
- 甘味の役割: 甘味には「補益(ほえき)作用」といって、体を滋養し、エネルギーや潤いを補う働きがあります。
この二つを組み合わせることで、酸味が潤いを体の中に「とどめ」、甘味がその潤いを「生み出す」という相乗効果が生まれ、効率的に体内の陰液を補充でき、熱を冷ますのに役立つと考えられています。
- 甘酸っぱい果物: りんご、梨、桃、ぶどう、トマト、梅など、それ自体が甘酸っぱい果物は、まさに「酸甘化陰」の食材です。
- ハチミツレモン: 運動後の水分補給や喉の乾燥に。
- 梅干しとお米: 梅干し(酸味)とご飯(甘味)の組み合わせは、食欲がない時や胃腸を休めたい時にも良いとされます。
- 酢豚や南蛮漬け: 甘酢あんや甘いマリネ液に、お酢(酸味)と砂糖(甘味)が使われています。
- フルーツビネガードリンク: 酢(酸味)と果物の甘み、はちみつなどを組み合わせたドリンク。
- 酢の物:きゅうりとわかめの酢の物や、タコの酢物も酸味、甘味に加え、海藻は身体の熱を冷ましたり、タコは暑さで消耗した身体を回復させるタウリンが豊富に含まれています。
- 寿司:酢飯もまさに気を補う米に、酸味、甘味が使われています。中や上に使われる具材のそれぞれの効果も期待できます。
特に、汗をたくさんかく暑い季節や、空気が乾燥する秋・冬には、体内の潤いが失われやすいため、「酸甘化陰」の考え方を取り入れた食事は非常に有効とされています。
夏のシーズンは、心と体のどちらか一方だけをケアするのではなく、両方が密接に影響し合っているという「心身一如」の視点から、総合的にバランスを整えることが、夏バテを防ぎ、健やかに過ごすための鍵となります。
⑤身土不二(しんどふじ)
人間が自然の一部であり、自らの体を育む環境と深く結びついているという考え方を表す言葉。
人間の体と、その体が育まれた土地(環境)は切り離せない関係にあり、今いる場所の気候風土で育った食べ物や、その土地の自然環境の影響を強く受けている。すなわち、その土地で、その季節に自然に育った食べ物を摂ることが、最も体にとって良い。という考え方。
よく似た言葉に地産地消という言葉があります。遠く離れた場所で育った食材や、季節外れの食材よりも、自分の住む地域の旬のものを食べることが、体がその環境に順応し、健康を保つ上で理想的であるとされます。
暑い季節には夏野菜(きゅうり、トマト、ナスなど)、果物(スイカ、梨)、豆類(緑豆)、豆腐、白きくらげなど、体の熱を冷まし、失われた陰液を補う食材を積極的に摂りましょう。また、前述しましたように、酸っぱい物と甘い物を一緒にとると津液の消耗を抑え、暑さへの抵抗力が増します。
その際には露地もの、地元で穫れたものを食べることが身土不二の考え方には沿っています。最近のスーパーでは地元で穫れた野菜のコーナーがあったり、道の駅、地元のJAが経営するスーパーなどがあります。このようなものを利用されるのもいいのではないでしょうか。
⑥扶正袪邪(ふせいきょじゃ)
扶正(ふせい): 「正気(せいき)」を助けること。正気とは、体が本来持っている抵抗力、免疫力、回復力、生命力といった、病気と闘い、健康を維持する力のことです。
袪邪(きょじゃ): 「邪気(じゃき)」を取り除くこと。邪気とは、病気の原因となる外部からの侵入(風邪、寒邪、湿邪、熱邪など)や、体内で生じる病理物質(痰、瘀血など)のことです。
つまり、「扶正袪邪」とは、体の抵抗力(正気)を高めつつ、病気の原因(邪気)を取り除くという意味のことば。
「扶正袪邪」は、病気を治すだけでなく、病気になりにくい体を作り、健康を維持するための、中医学の根本的な考え方と言えます。
- 正気を養う: 規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理など、基本的な健康習慣を心がけることで、体の抵抗力(正気)を高めることができます。
- 邪気を避ける・取り除く: 季節の変わり目に体調を崩さないよう服装に気をつけたり、体を冷やさないようにしたり、暴飲暴食を避けたりすることで、病気の原因(邪気)が体に入り込むのを防ぎ、また入ってしまった邪気は早めに解消するようにします。
次の冬病夏治・肥人多痰へと続きます。
⑦冬病夏治(とうびょうかち)
夏の間は症状が比較的落ち着いていることが多い、冬に悪化しやすい病気を、病気の勢いが弱まっている夏の時期に、体の陽気を高めたり、根本的な体質を改善する治療や養生を行うことで、次の冬の再発を防いだり、症状を軽くしたりすることを目指すことを意味する言葉。
- 季節の特性を最大限に活かした「予防医学」的なアプローチです。
- 冬に悪化しやすい冷え性、喘息、アレルギー性鼻炎、関節痛などは、体内の「陽気(ようき)」不足や「寒邪(かんじゃ)」の停滞が原因であることが多いです。
- 夏は、一年で最も自然界の陽気が盛んな時期です。この「陽気」の力を借りて、体内の冷えを取り除き、不足している陽気を補う(つまり扶正する)のに最適な時期と捉えます。
- 扶正の側面: 夏の強い陽気を活用して、冬に不足しがちな体の陽気を補い、根本的な体力を高めます。これは「扶正」のアプローチです。
- 袪邪の側面: 陽気を補うことで、体内に潜む「寒邪」や「痰湿」といった冬の病気の原因となる「邪気」を追い出したり、固まったものを柔らかくしたりする作用を促します。これは「袪邪」のアプローチです。
例えば、冷え性の人が夏に生姜などの体を温める食材を摂ったり、温灸をしたりするのは、まさに夏の陽気を借りて体内の陽気を補い(扶正)、冬の寒さに負けない体を作る(袪邪)という「冬病夏治」の実践であり、これは「扶正袪邪」の具体的な応用例なのです。
⑧肥人多痰(ひじんたたん)
肥満体質の人には、湿(しつ)痰(たん)が多い傾向があるという意味の言葉。
東洋医学では、体に役に立つ水を「津液」体に役に立たない水を「湿」、体内で処理しきれなかった余分な水分や老廃物が滞り、粘り気のあるヘドロのようなものになったものを「痰」といいます。この湿痰は、体内の水液代謝が滞ることで発生します。
また、この湿痰は一旦体内に生じるとなかなか外に追い出すことが困難で、万病の元になると言われています。
水分代謝は特に「脾」の働きが低下している場合に起こり、この言葉は、単に肥満を指している言葉ではなく、脾の働きを改善し、労わり、水分代謝を改善しないと体調不良につながるよ。と言うことを示しています。
前述の不正袪邪の考え方に照らし合わせると、
- 邪気(病気の原因): 体内に過剰に蓄積された湿痰や湿邪
- 正気(体の抵抗力): 湿痰を生み出す原因となった脾の気(脾気)の不足、つまり正気の不足
という状態にあると考えられます。
湿度の多い梅雨の季節や、暑い夏に冷たい食べ物・飲み物の摂り過ぎや、常日頃から、甘い物・油ものの食べ過ぎで胃腸に負担をかけ、胃腸の働きが低下している人はまさしくこの「肥人多痰」になりやすいので注意が必要です。
このような人は、
- 扶正(脾の気を補う): 湿痰が体内に溜まっている主な原因は、脾の機能が低下して水分をうまく代謝できていないことです。そのため、まず「正気」である脾の気を補い、その機能を高めることが重要です。
- 脾を健やかにする食事: 消化に良いもの、脾の働きを助ける食材(米、じゃがいも、山芋、きのこ類、鶏肉など)を摂る。
- 規則正しい食生活: 暴飲暴食を避け、胃腸に負担をかけない。
- 適度な運動: 気の巡りを良くし、脾の働きを助ける。
- 袪邪(湿痰を取り除く): 同時に、すでに体内に蓄積されてしまっている「邪気」である湿痰を取り除くことも必要です。
- 利湿・化痰作用のある食材: 冬瓜、はと麦、緑豆、大根、とうもろこし、海藻類などを積極的に摂る。
- 湿痰を増やすものを避ける: 脂っこいもの、甘いもの、冷たいもの、乳製品の過剰摂取は、湿痰をさらに生み出す原因となるため控える。
- 発汗: 運動や入浴などで適度に汗をかき、余分な水分を排出する。
⑨夜臥早起(やがそうき)
夜はやや遅めに寝て、朝は早く起きる(夏の自然なリズム)という意味のことば。
通常の「早寝早起き」とは異なり、夏の陽気の盛んな時期に適した睡眠リズムを示します。
日が長い夏は、夜の活動時間が長くなりがちで、早朝から日が昇り活動的になります。この自然のリズムに合わせて、少しだけ夜更かしし、朝早くから活動するという意味です。
ただし、これは十分な睡眠時間を確保した上での話であり、単なる「遅寝早起き」で睡眠不足になることを推奨するものではありません。あくまで、夏の陽気に合わせた柔軟な睡眠リズムのことを表しています。あくまで夏という季節の特性に合わせた「自然なリズム」を指します。
⑩避暑就涼(ひしょしゅうりょう)
暑さを避け、涼しい場所を選ぶ。という意味のことば。
文字通りの意味ですが、これも重要な夏の養生です。
夏の季節には無理に暑い場所で長時間過ごすことを避け、日陰や風通しの良い場所、あるいは適切に冷房を活用するなどして、体が過剰な熱を蓄えないようにすることが大切です。
これにより、熱中症を防ぎ、気や陰液の過度な消耗を防ぎます。
先達の知恵を現代の生活に活かせて健やかな夏を!
東洋医学には本日お伝えしたような先達の残した知恵がたくさんあります。
どれも、とても身近で腑に落ちる知恵ばかりです。
夏を出来るだけ健やかに過ごすことは、次の秋冬を健やかに過ごすことにも繋がります。
近年の酷暑は非常に心身を消耗してしまいますが、本日のこれらの先達の知恵をたまには思い出して、出来るだけ快適に過ごせるように工夫して毎日をお過ごしくださいね。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。
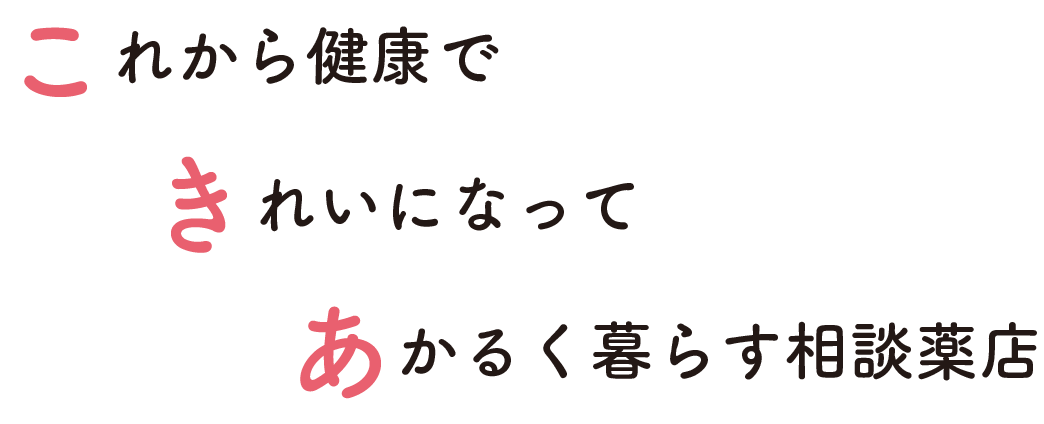

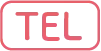 06-7897-7116
06-7897-7116