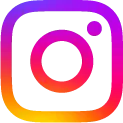今年も猛暑の日々ですね。
このような夏の暑さは紫外線と相まって、私たちの体に多大な酸化ストレスを与えます。
「夏を過ごした肌は10歳年をとる」・・・・これは昔受けた化粧品の勉強会で聞いた言葉です。衝撃過ぎて今でも忘れられません。
もちろん、これは肌だけでなく体全体に同じことがいえます。
本日はそんな過酷な夏に老化を進めないためにどうすればいいかを深堀していきます。このブログが夏を健やかに出来るだけダメージなく過ごしたい方にお役に立てることを願っています。

目次
夏はなぜ「老化の加速シーズン」なの?
夏と老化には非常に深い関係があります。夏の環境要因、特に紫外線と暑さは、私たちの体が本来持っている防御機構に大きな負担をかけ、老化を加速させる主要な原因となります。
1. 「光老化」:紫外線の蓄積が肌の老化の8割を占める
肌の老化の約8割は、加齢による自然な老化ではなく、長年にわたる紫外線の影響で起こる「光老化(ひかりろうか)」だとされています。夏は一年で最も紫外線が強く、この光老化を加速させる最大の要因となります。
- UVBによる表皮のダメージ:
- シミ・そばかす: UVBは、肌の表皮にあるメラノサイトを強く刺激し、シミやそばかすの原因となるメラニン色素の過剰な生成を促します。これが蓄積されると、肌の色むらや濃いシミとなって現れます。
- 肌バリア機能の低下と乾燥: UVBは、肌のバリア機能を担う角層細胞や細胞間脂質(セラミドなど)にダメージを与え、肌の水分保持能力を低下させます。その結果、肌は乾燥しやすくなり、敏感肌や肌荒れを引き起こしやすくなります。
- DNA損傷と皮膚がん: UVBは皮膚細胞のDNAに直接的な損傷を与え、この損傷が修復されずに蓄積されると、皮膚がんのリスクを高めます。
- UVAによる真皮のダメージ:
- しわ・たるみ: UVAは波長が長く、肌の真皮層(表皮の下の層)まで深く到達します。真皮には肌の弾力とハリを保つコラーゲンやエラスチンといった線維が豊富にありますが、UVAはこれらの線維を直接的に損傷したり、分解酵素の活性を高めたりします。これにより、肌の弾力性が失われ、深いしわやたるみの主な原因となります。
- 黄ぐすみ: UVAの影響で真皮のコラーゲンなどが変性すると、肌全体が黄色っぽくくすんで見える「黄ぐすみ」にもつながります。これは「糖化」とも関連が深いです。
- 活性酸素の大量発生: 紫外線が肌に当たると、そのエネルギーによって細胞内で活性酸素が爆発的に発生します。これらの活性酸素は、細胞膜、DNA、タンパク質(コラーゲン、エラスチンなど)を無差別に攻撃し、酸化させて損傷させます。これが肌の老化だけでなく、全身の細胞の老化を加速させる根本原因となります。
2. 暑さ(高温環境)による間接的な老化促進
紫外線だけでなく、夏の「暑さ」そのものも、体と肌に負担をかけ、老化の進行に関与します。
- 活性酸素の生成増加: 暑い環境下では、体温調節のために多くのエネルギーが消費され、細胞内のミトコンドリアの活動が活発になります。この過程で、副産物として活性酸素の発生量が増加します。また、脱水や電解質バランスの乱れも、細胞ストレスを増やし、活性酸素生成を促します。
- 肌の「隠れ乾燥」: 夏は汗や皮脂で肌がベタつきがちですが、実際は紫外線によるバリア機能の低下や、エアコンによる乾燥で肌内部は「隠れ乾燥」していることが多いです。肌が乾燥すると、外部刺激を受けやすくなり、小じわやハリ不足といったエイジングサインにつながりやすくなります。
- 睡眠不足とストレス: 熱帯夜による寝苦しさや、暑さによる身体的・精神的ストレスは、自律神経の乱れや睡眠不足を引き起こします。睡眠不足は、細胞の再生・修復機能を低下させ、免疫力も損なうため、老化の進行を加速させます。ストレスも活性酸素の生成を増加させる要因です。
- 糖化の促進: 夏は冷たい飲み物やアイスクリームなど、糖分を多く摂取しがちです。また、高温環境そのものも、体内でタンパク質と糖が結びつき、最終糖化産物(AGEs)を生成する「糖化」反応を促進する可能性があります。AGEsは、体内のコラーゲンなどを劣化させて弾力性を失わせ、黄ぐすみやしわ、たるみ、動脈硬化の原因となります。
このように、夏は紫外線による「光老化」と、暑さによる身体的ストレス、活性酸素の増加、隠れ乾燥、糖化の促進が複合的に作用し、肌だけでなく全身の老化を加速させる「老化の加速シーズン」と言えます。
肌と体を守るための外からの紫外線対策
1. 物理的な遮蔽:最も確実な防御策
肌に直接紫外線を当てないように、物理的に遮蔽する方法は、最もシンプルかつ効果の高い対策です。
- 日傘を活用する: 紫外線カット加工が施された日傘は、顔や首だけでなく、全身に降り注ぐ紫外線を広範囲にカットします。遮光率やUVカット率が高いものを選びましょう。
- つばの広い帽子をかぶる: 顔全体、特に日焼け止めを塗り忘れがちな額や頬、首の後ろ、耳までしっかりとカバーできます。つばが7cm以上あるものが効果的とされています。
- UVカット機能付き衣類を選ぶ: 長そでのシャツやパンツ、UVカット加工されたカーディガンなどを活用しましょう。特UPF(紫外線保護指数)が表示されている衣類は、その効果が数値で示されているため、信頼性が高いです。日常使いからアウトドアまで幅広く活用できます。
- サングラスをかける: 目から入る紫外線は、白内障や加齢黄斑変性などの目の病気のリスクを高めます。UV400(紫外線を99%以上カットする)表示のあるものや、「UVカット」の表示があるものを選びましょう。レンズの色が濃ければ良いわけではなく、紫外線カット率が重要ですし、レンズの色が濃すぎると瞳孔が開いてかえって紫外線を多く取り込んでしまうリスクもあるため注意が必要です。
- アームカバーや手袋をする: 車の運転中や自転車に乗る際など、腕や手の甲も紫外線ダメージを受けやすい部分です。専用のアームカバーや手袋を活用しましょう。
2. 日焼け止めの賢い使い方:効果を最大限に引き出す
日焼け止めは、紫外線を肌に到達させないための強力なツールですが、その効果は選び方と使い方に大きく左右されます。
- SPFとPAを理解する:
- SPF(Sun Protection Factor): 主にUVB(肌を赤く炎症させる紫外線)の防止効果を示します。数値が高いほど、UVBによる日焼け(サンバーン)を遅らせる時間が長くなります(例:SPF50+は「50より高い」ことを意味)。
- PA(Protection Grade of UVA): UVA(肌の奥に届き、しわやたるみの原因となる紫外線)の防止効果を示す指標で、「PA+」から「PA++++」まで4段階あります。「PA++++」が最も高い防止効果を示します。光老化対策には、PA++++を選ぶのがおすすめです。
- 選び方の目安: 日常使いならSPF20~30、PA+++程度で十分ですが、屋外でのレジャーやスポーツ、炎天下での活動にはSPF50+、PA++++を選ぶのが良いでしょう。
- 「たっぷり」と「ムラなく」塗る: 日焼け止めは、表示通りの効果を得るために、推奨量を守って塗ることが重要です。顔全体で1円玉大2個分、体も適量を守ってムラなく塗り広げましょう。少量だと効果が半減してしまいます。
- こまめに塗り直す: 汗や皮脂、摩擦によって日焼け止めは落ちてしまいます。特に汗をかきやすい夏場や屋外活動時は、2~3時間おきに塗り直すように心がけましょう。水に強いウォータープルーフタイプを選ぶのも有効です。
- 塗るタイミング: 外出の20~30分前には塗布を完了させ、肌になじませる時間を確保しましょう。
3. 時間帯と場所の考慮:紫外線を賢く避ける
紫外線の量が特に多い時間帯や場所を把握し、そこでの活動を工夫することも重要な対策です。
- 紫外線ピーク時間を避ける: 一年を通じて、午前10時から午後2時頃が最も紫外線量が多くなります。この時間帯の外出はなるべく避けたり、屋内での活動に切り替えたりする工夫をしましょう。
- 場所による注意:
- 地面からの反射: 砂浜(約10~25%反射)、アスファルト(約10%反射)、水面(約10~20%反射)など、地面からの反射光でも紫外線は強まります。※季節外れになりますが雪面は紫外線を約80%反射するため、スキーやスノーボード時には顔の下側や目の保護を徹底しましょう。
- 標高と緯度: 標高が高い場所や、赤道に近い地域ほど紫外線が強くなります。旅行先での対策も意識しましょう。
- 曇りの日や室内でも油断しない: UVAは曇りの日でも晴れの日の約80%が降り注ぎ、窓ガラスも透過します。年間を通して、室内でも日当たりの良い場所では油断せず、PA表示のある日焼け止めやUVカットカーテンなどを活用しましょう。
夏のダメージを最小限に抑えるためのインナーサポート
1. 食べる抗酸化対策:体内の防御システムを強化する
夏のインナーサポートの主役は、食事による抗酸化物質の積極的な摂取です。活性酸素の発生を抑え、発生したものを速やかに無害化するための「体内の消防士」を増やしましょう。
- 彩り豊かな野菜と果物:
- 理由: 野菜や果物の鮮やかな色は、それぞれ異なる種類の強力な抗酸化物質(ポリフェノールやカロテノイド)が豊富に含まれている証拠です。これらが相乗的に働き、体内の多様な活性酸素に対応します。
- 具体例: 赤パプリカ、ブロッコリー、トマト、ほうれん草、ブルーベリー、キウイなど。
- ビタミンCの積極的な摂取:
- 理由: 紫外線によって最も消費されやすいのがビタミンCです。強力な抗酸化作用に加え、コラーゲンの生成を助け、肌のハリや弾力を保つ、免疫機能を強化するなど、夏の体には欠かせない「万能ビタミン」です。
- 賢い摂り方: 水溶性で体内に蓄積されにくいため、一度に大量に摂るより、食事のたびにこまめに摂取するのが効果的です。熱に弱いので、生で食べたり、短時間の調理を心がけたりしましょう。
- ビタミンEとセレンの補給:
- 理由: ビタミンEは細胞膜の酸化を防ぐ「脂溶性の盾」。セレンは体内の重要な抗酸化酵素グルタチオンペルオキシダーゼの働きに不可欠なミネラルです。
- 具体例: ナッツ類、アボカド、植物油(ビタミンE)、魚介類、肉類、卵(セレン)。
- 良質なタンパク質と腸内環境の整備:
- 理由: 肌や細胞の修復には良質なタンパク質が不可欠です。また、腸内環境を整えることで、栄養素の吸収が促進され、免疫機能も正常に保たれやすくなります。
- 具体例: 肉、魚、卵、大豆製品、発酵食品(ヨーグルト、納豆など)。
- 控えたい食品:
- 理由: 加工食品、揚げ物、過度な糖分摂取は、体内で活性酸素の生成を促進したり、抗酸化物質の消費を増やしたりする可能性があります。
- 実践: これらを完全に避けるのではなく、量や頻度を意識して減らしましょう。
2. 質の良い睡眠:体の「修復工場」を稼働させる
睡眠は、単に体を休めるだけでなく、日中に受けたダメージを修復し、体内の防御システムを再起動させるための極めて重要な時間です。
- 理由: 睡眠中には、体内のターンオーバーが促進され、新しい細胞が作られます。また、細胞の修復や再生を促す成長ホルモンが分泌され、体内の抗酸化酵素の活性化も行われます。睡眠不足は、細胞の再生能力や免疫力を著しく低下させ、酸化ストレスへの抵抗力を弱めてしまいます。
- 実践: 毎日7〜8時間の睡眠を確保することを目標にしましょう。寝る前のデジタルデバイスの使用を控え、寝室の温度や湿度を快適に保つなど、睡眠の質を高める工夫をすることが大切です。
3. ストレスマネジメント:心と体のバランスを整える
精神的・身体的なストレスは、活性酸素を増やし、免疫機能やホルモンバランスを乱す大きな要因となります。
- 理由: ストレスを感じると分泌されるストレスホルモンは、体内の代謝に影響を与え、活性酸素の生成を促進します。また、ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、全身の血流や細胞機能にも悪影響を及ぼします。
- 実践: ストレスを完全にゼロにすることは不可能ですが、自分なりの解消法を見つけることが重要です。深呼吸、瞑想、軽い運動、趣味の時間、アロマテラピーなど、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。
4. 適度な運動と十分な水分補給:体の巡りを良くする
体の巡りを良くすることは、老廃物の排出を促し、細胞への酸素や栄養素の供給をスムーズにすることで、間接的に抗酸化システムをサポートします。
- 適度な運動:
- 理由: 定期的な適度な運動は、体内の抗酸化酵素の活性を高めることが知られています。また、血行促進効果で新陳代謝が活発になります。
- 実践: ウォーキングやジョギングなど、無理のない範囲で毎日20~30分程度の有酸素運動を心がけましょう。過度な運動はかえって活性酸素を増やすことがあるため注意が必要です。
- 十分な水分補給:
- 理由: 夏は特に汗をかくため、脱水状態になりやすく、これが細胞ストレスや活性酸素の増加に繋がります。適切な水分補給は、体内の代謝をスムーズにし、老廃物の排出を促します。
- 実践: のどが渇く前に、こまめに水やお茶を飲みましょう。特に、起床時、入浴前後、運動前後、就寝前などは意識して水分を摂るようにしましょう。
夏のダメージを最小限に抑えるインナーサポートは、特別なことではなく、日々の生活習慣の積み重ねです。体の内側から強く、健康的な状態を保つことで、肌も体も夏の過酷な環境に負けない力をつけることができます。
体を酸化ストレスから守る「抗酸化システム」:内なる防御メカニズムの全貌
私たちの体は、生命活動の過程で避けられない「活性酸素」の発生に、無防備なわけではありません。むしろ、そのダメージから細胞を守るために、非常に精巧で多層的な「抗酸化システム」という総合的な防御メカニズムを生まれつき備えています。これは、体内で発生する活性酸素を無害化する「内因性抗酸化システム(体内酵素)」と、食事から補給する「外因性抗酸化システム(抗酸化物質)」が連携し合うことで成り立っています。
その総合的な防御メカニズムを解説します。
1. 「活性酸素処理工場」:抗酸化酵素の連携プレイ
体内で発生する活性酸素を直接分解し、無害な物質に変換する、まさに「活性酸素処理工場」のような役割を果たすのが、以下の抗酸化酵素たちです。これらはチームとして連携し、段階的に活性酸素を無害化します。
a. SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)
- 役割の第一段階: 最も基本的な活性酸素であるスーパーオキシド(O2⋅−)を標的とします。スーパーオキシドは、ミトコンドリアでのエネルギー産生過程で常に発生する最初の活性酸素です。
- 変換作用: SODは、このスーパーオキシドを、比較的毒性の低い過酸化水素(H2O2)と酸素(O2)に変換します。
- 特徴: 活性に必要なミネラルとして、銅、亜鉛、マンガンなどがあります。体内のSODの働きは、これらのミネラルの摂取量にも影響されます。
b. カタラーゼ
- 役割の第二段階(主な処理役): SODによって生成された過酸化水素(H2O2)を分解する主要な酵素です。過酸化水素もそのままでは細胞にダメージを与えるため、速やかな処理が必要です。
- 変換作用: カタラーゼは、過酸化水素を完全に無害な水(H2O)と酸素(O2)に分解します。
- 特徴: 主にペルオキシソームという細胞小器官に高濃度で存在し、特に大量の過酸化水素が発生する場所で迅速に働きます。
c. グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)
- 役割の第二段階(多機能処理役): カタラーゼと同様に過酸化水素(H2O2)を水に分解する酵素ですが、さらに厄介な脂質過酸化物(細胞膜の脂質が酸化されたもの)を還元し、無害化する重要な役割も担っています。
- 連携と消費: この酵素が働く際には、還元型グルタチオン(GSH)という別の抗酸化物質を消費します。グルタチオンは体内で合成されるペプチドですが、その再生には様々な栄養素が必要です。
- 特徴: 活性に必要なミネラルとして、セレンが不可欠です。セレンが不足すると、この重要な酵素の働きが低下し、体内の酸化ストレスが高まる可能性があります。
【連携イメージ】 ミトコンドリアでスーパーオキシド発生 → SODが過酸化水素に変換 → カタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼが水と酸素に分解。この一連の流れで、活性酸素は連鎖的に無害化されていきます。
2. 「補充と再生のネットワーク」:非酵素系抗酸化物質のサポート
抗酸化酵素だけではカバーしきれない、あるいは酵素の働きを助け、再生させる役割を担うのが、体内で合成される、あるいは食事から摂り入れる非酵素系抗酸化物質です。これらは「抗酸化ネットワーク」を形成し、互いに協力し合って活性酸素を消去します。
a. グルタチオン
- 「マスター抗酸化物質」: 体内で合成されるペプチドで、細胞内に高濃度で存在します。直接活性酸素を消去するだけでなく、特にグルタチオンペルオキシダーゼの補酵素として不可欠です。
- 解毒作用: 肝臓での解毒作用にも深く関与し、体内の有害物質の排出を助けることで、間接的に酸化ストレスを軽減します。
b. コエンザイムQ10
- エネルギー産生と抗酸化の両立: ミトコンドリア内でエネルギーを生み出す過程に必須の補酵素ですが、同時に強力な脂溶性の抗酸化作用を持ち、ミトコンドリア自身を活性酸素のダメージから守ります。
- 特徴: 体内で合成されますが、加齢とともに合成能力が低下するため、食品やサプリメントからの補給が重要になります。
c. α-リポ酸
- 「万能な抗酸化物質」: 水溶性・脂溶性の両方の性質を持つため、細胞のあらゆる場所で抗酸化作用を発揮できます。
- 他の抗酸化物質の再生: 酸化されたビタミンCやビタミンE、グルタチオンなどを再生させる能力を持ち、抗酸化ネットワークの効率を高めます。
d. 尿酸
- 意外な抗酸化力: 痛風の原因としても知られる尿酸ですが、体液中においては強力な抗酸化作用を持つことが分かっています。過剰な活性酸素を消去し、DNAの酸化を防ぐ役割を担います。ただし、高すぎると弊害があるため、そのバランスが重要です。
3. 「外部からの援軍」:食事由来の抗酸化物質
体内のシステムだけでは対処しきれない活性酸素の増加や、酵素の働きをサポートするために、食事から積極的に摂取すべき抗酸化物質も、この総合システムの一部です。これらは「外因性抗酸化システム」として、体内の防御力を強化します。
- ビタミンC: 水溶性で、体液中の活性酸素を直接消去するほか、酸化されたビタミンEなどを再生させる「抗酸化ネットワーク」のハブ役。
- ビタミンE: 脂溶性で、細胞膜の脂質が酸化されるのを防ぐ「細胞膜の守り神」。
- ポリフェノール類: 植物由来の色素や苦味成分で、多種多様な抗酸化作用を持ち、抗炎症作用など複合的な健康効果も期待されます(例: アントシアニン、カテキン、レスベラトロールなど)。
- カロテノイド類: 赤、黄、橙色の色素成分で、特にアスタキサンチン(強力な抗酸化力)、ルテイン(目の保護)、リコピン(前立腺や美肌)などが有名。
抗酸化力の高い食べ物・健康食品にはどんなものがあるの?
「抗酸化力」とは、体内の酸化ストレスを軽減し、細胞の損傷を防ぐ能力のことです。これは、老化や様々な病気の予防に繋がると言われています。ただし、食品の抗酸化力は、調理法や摂取量、個人差によって変動するため、厳密な「高い順」を決定することは非常に困難です。しかし、一般的には次のようなものが抗酸化力が高いといわれています。
1. ポリフェノール類が豊富なもの
ポリフェノールは非常に多様な種類があり、それぞれ異なる抗酸化作用を持っています。
- アサイー、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリーなどのベリー類:特にアントシアニンが豊富で、強力な抗酸化作用を持ちます。
- カカオ(ダークチョコレート):フラボノイドが非常に豊富で、心血管系の健康にも良いとされます。カカオ含有量が高いほど抗酸化力も高い傾向にあります。
- 緑茶、抹茶:カテキン(特にエピガロカテキンガレート:EGCG)が豊富で、がん予防や代謝促進効果も期待されています。
- コーヒー:クロロゲン酸というポリフェノールが豊富で、抗酸化作用だけでなく、血糖値の上昇を抑える効果も報告されています。
- 赤ワイン:レスベラトロールなどのポリフェノールを含みます。適量を摂取することが推奨されます。
- ザクロ:アントシアニンやエラグ酸などが豊富で、強い抗酸化作用があります。
- ナッツ類(アーモンド、くるみなど):ビタミンEやポリフェノールを含みます。
- 野菜(特に色が濃いもの):
- ほうれん草、ケールなどの葉物野菜:ルテインやゼアキサンチン、β-カロテンなどが豊富です。
- ブロッコリー、カリフラワー:スルフォラファンなどのイソチオシアネート類が含まれます。
- トマト:リコピンが有名で、特に加熱調理することで吸収率が高まります。
- パプリカ:ビタミンCやカロテノイドが豊富です。
2. カロテノイド類が豊富なもの
主に赤色、黄色、橙色の色素成分です。
- アスタキサンチン(例:鮭、いくら、エビ、カニ):非常に強力な抗酸化力を持つことで知られ、目の健康や美肌効果も期待されています。サプリメントとしても人気があります。
- リコピン(例:トマト、スイカ、ピンクグレープフルーツ):特に前立腺の健康に良いとされます。
- β-カロテン(例:人参、カボチャ、ほうれん草):体内でビタミンAに変換され、抗酸化作用を発揮します。
3. ビタミン類
ビタミン自体が抗酸化作用を持つものや、抗酸化酵素の働きを助けるものがあります。
- ビタミンC(例:柑橘類、イチゴ、キウイ、ブロッコリー、パプリカ):水溶性の強力な抗酸化物質で、コラーゲンの生成にも関与します。
- ビタミンE(例:ナッツ類、植物油、アボカド、ほうれん草):脂溶性の抗酸化物質で、細胞膜の酸化を防ぎます。
4. その他
- セレン(例:ブラジルナッツ、魚介類、肉類):抗酸化酵素の構成成分となり、体内の抗酸化システムをサポートします。
- コエンザイムQ10(例:肉類、魚介類、ナッツ類):細胞のエネルギー産生に関わり、強力な抗酸化作用も持ちます。体内でも合成されますが、加齢とともに減少します。健康食品としても利用されます。
摂取のポイント
- 多様な食品を組み合わせる: 特定の食品に偏らず、様々な色の野菜、果物、ナッツ、豆類などをバランス良く摂ることが重要です。異なる抗酸化物質が相乗的に働くことで、より効果が高まります。
- 旬のものを食べる: 旬の野菜や果物は、栄養価が高く、抗酸化物質も豊富に含まれている傾向があります。
- 加熱調理の工夫: リコピンのように加熱することで吸収率が高まるものもあれば、ビタミンCのように熱に弱いものもあります。調理法にも注意しましょう。
- 加工食品を控える: 加工度の高い食品は、抗酸化物質が失われていることが多いだけでなく、添加物などが含まれている可能性もあります。
- 健康食品やサプリメントの活用: 食事だけでは不足しがちな栄養素や、特定の抗酸化物質を補給するために、健康食品やサプリメントを検討することも有効です。ただし、過剰摂取は避けて、信頼できる製品を選び、必要に応じて医師や薬剤師に相談しましょう。
最も強力な抗酸化物質ベスト5
- 試験管内での測定結果(特にORAC値など)において、非常に高い数値が報告されていること。
- 生体内での研究(動物実験やヒトでの臨床試験)において、目の健康、美肌、疲労回復など、多岐にわたる効果が確認されていること。
これらの点から、以下のようなものが比較的強力な抗酸化物質であるといわれています。
1. アスタキサンチン
アスタキサンチンは、カロテノイドの一種で、鮭、エビ、カニなどに含まれる赤い色素です。その抗酸化力は、ビタミンEの約1000倍、β-カロテンの約40倍、コエンザイムQ10の約150倍とも言われ、非常に強力な抗酸化作用を持つことで広く知られています。特に、脂溶性であるため細胞膜を強力に保護し、目の健康、美肌効果、疲労回復など、多岐にわたる効果が期待されています。
2. アントシアニン
ブルーベリー、アサイー、ラズベリー、ブラックベリーなどのベリー類に豊富に含まれるアントシアニンも、その強力な抗酸化力で知られています。特にアサイーは「スーパーフード」として注目され、その抗酸化力の高さが評価されています。アントシアニンは目の疲れの軽減や、血管の健康維持にも良いとされています。
3. カテキン(特にEGCG)
緑茶や抹茶に豊富なカテキン、特にエピガロカテキンガレート(EGCG)(緑茶に含まれるカテキンの約50〜60%をEGCGが占めています)は、非常に強力な抗酸化作用を持つことで知られています。がん予防や心血管疾患のリスク低減、代謝促進など、様々な健康効果が研究されています。
4.βカロテン
特に光化学反応(特に紫外線が肌に当たる際など)で発生しやすく、細胞膜の脂質やDNAにダメージを与える強力な活性酸素種である一重項酸素(1O2)を消去する能力に非常に優れているとされています。体内でビタミンAに変換されるため、多面的な健康効果も期待できます。ニンジン、カボチャ、ほうれん草、パプリカなどの緑黄色野菜から、油を使った調理法や加熱調理で効率よく摂取できます。
5.ビタミンCの抗酸化力と特徴
ビタミンCは抗酸化物質の「キング」とも呼ばれるほど、非常に重要な位置を占めています。
ビタミンCの抗酸化力と特徴
- 水溶性の抗酸化物質であること: アスタキサンチンやルテインが主に脂溶性であるのに対し、ビタミンCは水溶性です。この特性により、細胞質や血液、細胞間の液体など、体内の水分の多い場所で活性酸素を消去する役割を担っています。これにより、細胞のDNAやタンパク質などの水溶性の成分が酸化ダメージを受けるのを防ぎます。
- 直接的な活性酸素消去能力: ビタミンCは、スーパーオキシド、ヒドロキシラジカル、一重項酸素など、様々な種類の活性酸素を直接捕獲し、無害化する能力を持っています。自身が電子を与えることで酸化されますが、最終的には体外に排出されるか、別の抗酸化物質によって再生されます。
- 他の抗酸化物質の再生を助ける「抗酸化ネットワーク」の中心: ビタミンCが特に「強力」と言われる理由の一つは、他の抗酸化物質の働きをサポートし、再生させる能力にあります。
- 例えば、ビタミンEが脂質の酸化を防ぐ際に自身が酸化されますが、酸化されたビタミンEをビタミンCが還元し、再び抗酸化力を回復させることができます。
- これにより、体内の抗酸化システム全体が効率的に機能するのを助け、「抗酸化ネットワーク」の要として働きます。
- コラーゲン生成に必須: 抗酸化作用とは少し異なりますが、ビタミンCはコラーゲン(皮膚、骨、血管などを構成する重要なタンパク質)の生成に不可欠な栄養素です。これにより、皮膚の健康や血管の弾力性維持にも貢献し、間接的に酸化ダメージからの回復や予防にも役立ちます。
6.様々な種類の抗酸化物質をバランス良く摂取することが大切
これらの物質は、それぞれ異なるメカニズムで体内の酸化ストレスと戦います。単一の「最強」にこだわるのではなく、様々な種類の抗酸化物質をバランス良く摂取することが、総合的な健康維持には最も効果的です。例えば、アスタキサンチンは脂溶性なので細胞膜の保護に優れ、ビタミンCは水溶性で細胞内の液体の酸化を防ぐといった具合に、それぞれが異なる役割を担っているからです。
こきあ相談薬店がおススメする夏の抗酸化対策
1.ビタミンC:前述のとおり抗酸化物質の「キング」とも呼ばれるビタミンC。こきあ相談薬店が取り扱っておりますビタミンC製剤は瀬戸内て穫れたレモン果汁と大分のカボス果汁が入った、1包に1000mgのビタミンCを含む、とてもおいしい製剤です。
2.コエンザイムQ10:細胞のエネルギー産生に関わり、強力な抗酸化作用も持つコエンザイムQ10。こきあ相談薬店で取り扱っている製剤は還元型コエンザイムQ10がコショウ由来成分と紅蔘配合により吸収しやすくなっています。
3.大麦若葉(βカロテン):β-カロテン以外にも、大麦若葉には現代人が不足しがちな様々な栄養素がバランス良く含まれています。クロロフィル: 緑色の色素で、体内のデトックス作用や消臭作用も期待されます。食物繊維: 豊富に含まれており、腸内環境の改善や便通の促進に役立ちます。ビタミン類: ビタミンC、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、ビタミンB群(B1, B2, B6など)なども含まれています。ミネラル類: カルシウム、鉄、カリウム、マグネシウム、亜鉛などが含まれます。SOD酵素: 活性酸素を分解する働きを持つ「SOD酵素(スーパーオキシドディスムターゼ)」も含まれています。こきあ相談薬店が取り扱っている大麦若葉製剤は国内でも3社しかないコールドプレス製法を用いた製剤です。
4.牡蠣肉エキス:「海のミルク」とも呼ばれる牡蠣の栄養を凝縮したものです。DHMBA(3,5-dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol)という、最近発見された牡蠣肉エキスの独自成分が入っており、強力な抗酸化能を持つと報告されています。DHMBAは水にも油にも溶ける「両親媒性」という特性を持つため、細胞膜などの脂質部分にも、細胞内の水溶性部分にも浸透し、細胞の奥深くで発生する活性酸素までしっかり捕捉して無害化すると考えられています。さらにはタウリン、亜鉛、セレン、グリコーゲン、鉄などの各種ビタミン・ミネラルといった40種類以上もの栄養素がバランス良く凝縮されています。こきあ相談薬店が取り扱っている製剤は取り扱い歴20数年、お手頃価格の製剤です。
5.核酸:核酸(特にDNAの材料となる核酸関連物質やヌクレオチド)を体外から補給することで、細胞は損傷したDNAを修復したり、新しい健康な細胞に作り変えたりする材料を得ることができます。また、核酸そのもの、あるいは核酸の構成要素であるプリン塩基やピリミジン塩基、ヌクレオチドなどには、活性酸素を直接捕獲して無害化する(スカベンジャー)能力があることが研究で示唆されています。こきあ相談薬店で取り扱っている核酸製剤は国内唯一の核酸原料メーカーの製剤です。
夏という季節を最大限に楽しみましょう!
夏の紫外線と活性酸素は避けられないものですが、今回ご紹介した、体内で発生する活性酸素を無害化する「内因性抗酸化システム(体内酵素)」と、食事から補給する「外因性抗酸化システム(抗酸化物質)」を最大限活用しながら抗酸化対策をして夏のダメージを最小限に抑えましょう。
そして、肌は美しく、体は内側から元気な状態を保ちながら、夏という季節を最大限に楽しみましょう!
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします。
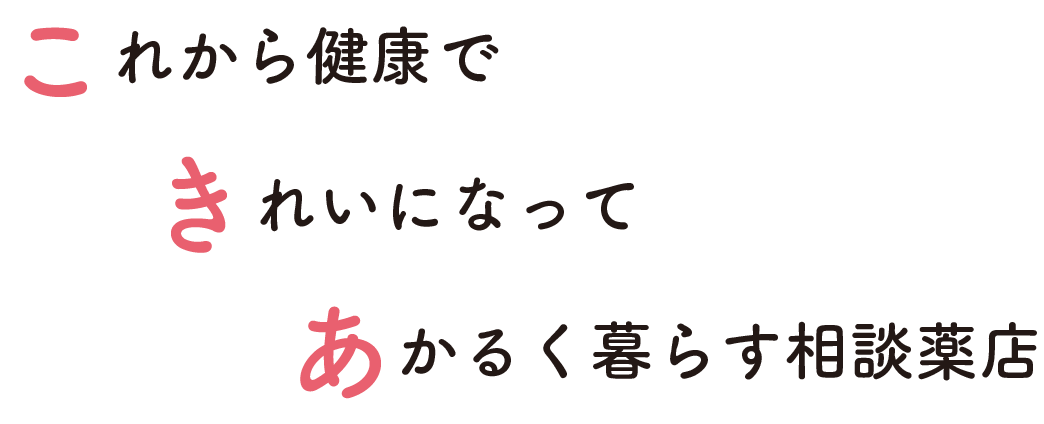

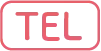 06-7897-7116
06-7897-7116