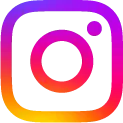皆さんは口内炎に悩まされた経験はありますか?
舌の先にできて食事のたびに激痛が走ったり、頬の内側にできて喋るのも億劫になったり……。歯ブラシが口内炎に当たった時には、もう、飛び上がるくらいの痛みですよね。
多くの方が一度は経験する、あの不快な症状や痛みはとても辛いものです。
店主の徳永薬剤師(私の娘)は小さなころからしょっちゅう口内炎ができ、口腔内に貼るパッチの薬が我が家には欠かせませんでした。
ところが、徳永薬剤師自身も、やがてこちら(漢方の勉強や相談薬店での仕事)の道に進み、口内炎と体の関係を理解し、養生をするようになると、「そういえば最近口内炎が出来ていない!!」ということに、ハタと気が付いたようです。
本日はそんな徳永や私の若かりし頃の体験をまじえ、口内炎と体の関係についてお話します。
このブログが口内炎に悩んでおられる方の参考にしていただけることを願っています。

目次
西洋医学から見た口内炎:原因はストレス?栄養不足?
まずは、西洋医学的視点から私たちが一般的に認識している口内炎の原因について見ていきます。
西洋医学では、口内炎は主に以下のような要因によって引き起こされると考えられています。
1. 免疫力の低下
過労や睡眠不足、ストレスは、私たちの体の免疫力を著しく低下させます。
免疫システムが弱まると、普段は悪さをしない口の中の常在菌が増殖したり、外部からの刺激に対して過敏に反応しやすくなり、結果として口内炎が発生しやすくなります。
2. 栄養不足
特にビタミンB群(B2、B6など)やビタミンC、鉄分、亜鉛などの栄養素が不足すると、皮膚や粘膜の健康が損なわれ、口内炎ができやすくなります。
偏った食生活やダイエットなどが原因となることも少なくありません。
3. 物理的な刺激
誤って頬の内側を噛んでしまったり、硬い食べ物で傷つけたり、熱いものを食べてやけどしたりするなど、直接的な物理的刺激によって口内炎ができることがあります。
また、合わない入れ歯や矯正器具が原因となるケースもあります。
4. ストレスと生活習慣の乱れ
精神的なストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良や消化機能の低下を引き起こします。
これにより、口腔内の粘膜の修復能力が落ち、口内炎ができやすくなります。不規則な生活や喫煙、過度の飲酒なども同様に悪影響を与えます。
5. その他の病気や薬の影響
まれに、ベーチェット病やクローン病などの全身疾患の一症状として口内炎が現れることがあります。
また、特定の薬剤の副作用で口内炎ができるケースも存在します。
繰り返しできる、治りが悪い、数が非常に多いといった場合は、医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。
西洋医学的には、まず症状を特定し、それに対して直接的な治療を行います。
対症療法としての薬の塗布や、ビタミン剤などの服用、栄養指導などがこれにあたります。
しかし、繰り返す口内炎の場合、「なぜ何度もできるのか」という根本原因に目を向ける必要があります。
そこで、東洋医学的考え方が大いに役立ちます。
東洋医学の視点:口内炎は「五臓六腑」の不調を映し出す鏡
東洋医学では、人間の体は「気(生命エネルギー)」「血(栄養物質)」「水(体液)」という3つの要素がバランス良く巡ることで健康が保たれると考えられています。
そして、これらは五行論の「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」と呼ばれる臓器に密接に関連しており、口内炎もまた、それらのうちのある臓器の不調や、気・血・水の乱れが口腔内の粘膜に現れたものと捉えます。
東洋医学の診断では、口内炎のできる場所や色、形、痛みの程度などが重要な手がかりとなります。
具体的な「五臓」との関係は以下のようになります。
1. 「心(しん)」の不調:舌にできる口内炎は心のサイン?
東洋医学における「心」は、西洋医学の心臓のポンプ機能だけでなく、精神活動や意識、血液の循環全体を司ると考えられています。特に、「心は舌に開竅(かいきょう)する」と言われ、心の状態は舌に反映されやすいとされます。
- 特徴: 舌の先や側面に赤く、痛みの強い口内炎ができることが多いです。熱を帯びているように感じたり、灼熱感(シャクネツカン)を伴うこともあります。
- 考えられる体の状態: 精神的なストレス、緊張、イライラ、不眠、動悸、多夢(夢を多く見る)など、「心の熱」がこもっている状態です。過度な思考や情報過多も心の負担となり、熱を生み出すことがあります。
- 体からのメッセージ: 「心が疲れ切っているよ」「休む時間が必要だよ」「考えすぎだよ」というSOS。
現代社会はストレスに満ち、心に大きな負担がかかりやすい環境です。舌にできる口内炎は、あなたの心が休息を求めているサインかもしれません。
口内炎ほどではなくても、心に負担がかかっている人、かかっている時は舌の先が赤くなっていることが多いです。
2. 「脾胃(ひい)」の不調:口の周りや唇の口内炎は胃腸のSOS!
「脾」と「胃」は、東洋医学において消化吸収の中心的な役割を担う臓器です。飲食物から「気」と「血」を作り出し、全身に供給する重要な働きをしています。「口は脾胃に開竅する」と言われ、脾胃の状態は口の周りや唇に現れやすいとされます。
- 特徴: 唇の内側や外側、口角、歯茎にできる口内炎が多いです。潰瘍のようなえぐれた形になることもあります。食欲不振、胃もたれ、下痢や便秘など消化器系の不調を伴うことが多いです。
- 考えられる体の状態: 消化不良、食べ過ぎ、冷たいものの摂りすぎ、不規則な食事時間などにより、脾胃の機能が低下している状態です。栄養の吸収が悪くなり、全身のエネルギー不足にもつながります。また、「湿熱(しつねつ)」といって、体内に余分な熱と湿気(老廃物)がこもっている状態も口内炎の原因となります。
- 体からのメッセージ: 「胃腸が疲弊しているよ」「食生活を見直してね」「体を冷やしすぎないでね」というSOS。
外食が多く、冷たい飲み物を好む方、早食いの習慣がある方は、脾胃に負担をかけている可能性があります。口の周りの口内炎は、消化器系からのストップサインかもしれません。
また、口内炎だけでなく、口の周りによくできるニキビや湿疹も脾胃の調子が低下、とくに湿熱により胃腸の機能が低下し、体内に熱がこもっている状態と考えられます。
3. 「腎(じん)」の不調:なかなか治らない口内炎は「精」の消耗?
東洋医学の「腎」は、西洋医学の腎臓の機能に加え、生命活動の根源となる「精(せい)」を蓄え、成長・発育、生殖、老化、水分代謝などを司る非常に重要な臓器です。「腎は二陰に開竅し、骨を主り、髪を潤す」と言われるように、腎の不調は全身の生命力に影響します。
- 特徴: 慢性的に繰り返す、治りにくい、深い、または多数の口内炎が見られることがあります。口全体にできることもあります。口の乾燥や喉の渇き、足腰の痛み、耳鳴り、頻尿、白髪などの老化現象を伴うことが多いです。
- 考えられる体の状態: 加齢、過労、睡眠不足、慢性的な病気などにより、体の根本的なエネルギーである「精」が消耗している状態です。体の潤いが不足する「陰虚(いんきょ)」の傾向がある場合も、熱がこもりやすくなり口内炎につながることがあります。
- 体からのメッセージ: 「生命エネルギーが不足しているよ」「無理をしすぎだよ」「休息を十分にとってね」というSOS。
なかなか治らない口内炎は、体の奥深くからのサインかもしれません。生活習慣を見直し、根本的な体力の回復に努める必要があります。
4. 「肝(かん)」の不調:側面にできる口内炎はイライラが原因?
東洋医学のでは「肝」は、血液の貯蔵と調節、気の巡りの管理、精神状態の安定などを司る臓器です。ストレスと密接に関係しており、「肝は目に開竅し、筋を主る」と言われます。
- 特徴: 頬の内側や、奥歯に近い側面にできる口内炎が多いです。イライラや怒り、ストレスを感じやすい時にできやすく、口が苦く感じたり、目の疲れ、肩や首のこり、頭痛、PMS(月経前症候群)などの症状を伴うことがあります。
- 考えられる体の状態: ストレスや怒り、抑圧された感情などにより「肝の気」が滞り、熱を帯びている状態です。気がスムーズに流れず停滞すると、熱に変わり、口内炎として現れることがあります。
- 体からのメッセージ: 「ストレスが溜まっているよ」「気分転換が必要だよ」「発散する場所を見つけてね」というSOS。
現代社会では、多くの方がストレスを抱えやすい傾向にあります。肝の不調による口内炎は、そうしたストレスが体に与える影響を教えてくれています。
暑い季節は口内炎が出来やすい!
暑さによる脱水と口腔内の乾燥、食欲不振とそれによる栄養不足、睡眠不足と疲労の蓄積、冷たいものの摂りすぎによる胃腸の負担などにより、夏場は口内炎が出来やすくなります。さらに東洋医学的には、以下のように考えます。
- 暑邪(しょじゃ)による「熱」の発生:
- 夏の「暑邪」は、体内に熱をこもらせやすい性質があります。特に、「心(しん)」や「胃(い)」に熱がこもりやすくなります。
- 心熱: 暑さでイライラしたり、寝苦しさで不眠が続いたりすると、「心」に熱がこもります。これが舌の先などに口内炎として現れることがあります。
- 胃熱: 暑いからといって辛いものや脂っこいものを食べ過ぎたり、熱中症で体に熱がこもったりすると「胃」に熱が生じます。口全体や唇、歯茎に口内炎ができやすくなります。
- 湿邪(しつじゃ)による「湿熱」の発生:
- 日本の夏は高温多湿。この湿気が「湿邪(しつじゃ)」として体内に侵入し、体の水の巡りを悪くします。
- 湿邪は、体が暑邪によって熱を帯びている状態と結びつき、「湿熱(しつねつ)」というやっかいな状態を作り出します。
- 脾胃湿熱(ひいしつねつ): 消化器系である「脾胃」に湿熱がこもると、口の周りにニキビができやすくなるのと同様に、口内炎もできやすくなります。胃もたれ、体がだるい、むくみやすいといった症状を伴うことが多いです。冷たいものの摂りすぎや過食も湿熱を助長します。
- 「気」の消耗と「陰液」の不足:
- 暑さで汗をたくさんかくことは、体に必要な「気(エネルギー)」と「陰液(体を潤す水分)」を消耗させます。
- 「気虚(ききょ)」や「陰虚(いんきょ)」の状態になると、体のバリア機能が低下し、粘膜が弱くなって口内炎ができやすくなります。特に「陰虚」は、体が乾燥しやすくなるため、口の渇きを伴う口内炎が繰り返されることがあります。
若い年代に口内炎ができやすいのはなぜ?
私の経験上、口内炎がよくできて悩んでおられるのは、男女を問わず10~30代の方が多いように思います。
実際に徳永もそうですし、私自身も振り返ってみればその年代にはよく口内炎が出来ていた記憶があります。
それではなぜ、若い年代に口内炎ができやすいのでしょうか。
西洋医学では、前述のように口内炎は免疫力や栄養状態、生活習慣に深く関連すると考えられています。若い年代特有のライフスタイルが、口内炎の発生リスクを高める要因となることがあります。
1.生活習慣の乱れと免疫力低下
- 睡眠不足・不規則な生活: 学生であれば試験勉強やアルバイト、社会人であれば仕事の多忙さや残業、夜間の娯楽などで、睡眠時間が削られたり、生活リズムが不規則になったりしがちです。これにより、体の免疫力が低下し、口内炎ができやすくなります。
- ストレス: 進学、就職、人間関係、仕事のプレッシャーなど、若い年代は新しい環境や役割に直面することが多く、精神的なストレスを感じやすい時期です。ストレスは自律神経のバランスを崩し、免疫機能の低下や血行不良を招き、口内炎の原因となります。
- 偏った食生活: 外食やコンビニ食が増えたり、インスタント食品に頼りがちになったりすることで、栄養バランスが偏りやすくなります。特に、粘膜の健康維持に必要なビタミンB群やC、鉄分、亜鉛などが不足しがちです。また、甘いものや刺激物、ジャンクフードの過剰摂取も消化器系に負担をかけ、間接的に口内炎につながることがあります。
2. ホルモンバランスの変化
思春期から成人にかけて、ホルモンバランスが大きく変動する時期でもあります。特に女性は生理周期やストレスによってホルモンバランスが乱れやすく、これが口内炎だけでなく、ニキビなどの肌トラブルにも影響することがあります。
3. 物理的な刺激
活動的な年代ゆえに、スポーツ中の接触や、食事中に誤って口の中を噛んでしまうといった物理的な刺激を受ける機会も多いかもしれません。また、歯科矯正をしている場合も、器具が粘膜に当たり口内炎を引き起こすことがあります。
「若い年代の口内炎」東洋医学から見ると
東洋医学では、若い年代に頻繁に口内炎ができるのは、主に「実証(じっしょう)」と呼ばれる状態、特に「熱」が体にこもりやすい体質や生活習慣が関係していると捉えられます。
若い年代は一般的に、生命エネルギーである「気」が旺盛で、体が熱を作りやすい傾向にあります。この「熱」が、さまざまな要因で体内にこもり、口内炎として現れるのです。
1. 「心熱(しんねつ)」と「肝火(かんか)」:ストレスや感情の蓄積
若い年代は、精神的な活動が活発で、ストレスを感じやすい時期でもあります。
- 心熱: 過度な思考、精神的な緊張、心配事、夜更かしなどにより「心」に熱がこもる状態です。これにより、舌の先端や側面に赤く痛みの強い口内炎ができやすくなります。
- 肝火(かんか): ストレス、怒り、イライラ、感情の抑圧などにより「肝」の気が滞り、熱に変わる状態です。口の側面や頬の内側にできやすく、目の充血や頭痛、肩こりなどを伴うこともあります。
これらは、現代社会を生きる若い世代が抱えやすい心の問題が、身体症状として現れていると考えることができます。
2. 「胃熱(いねつ)」と「脾胃湿熱(ひいしつねつ)」:食生活の乱れ
若い年代は、交際範囲が広がり、食事も外食や嗜好品に偏りがちになることがあります。
- 胃熱: 暴飲暴食、辛いものや脂っこいものの過剰摂取、アルコールなどにより、胃に熱がこもる状態です。口全体や唇、歯茎にできやすく、口臭や便秘を伴うこともあります。
- 脾胃湿熱: 胃熱に加えて、甘いもの、冷たいものの摂りすぎ、消化の悪いものの常食などにより、体内に余分な「湿(老廃物)」が停滞し、熱と結びついた状態です。口の周りや唇のニキビと同じく、口のねばつき、胃もたれ、下痢や便秘などを伴うことが多いです。
これらは、不規則な食生活や偏った食の好みが、消化器系に負担をかけ、体内の炎症として口内炎に現れていると考えられます。
3. 「陰虚火旺(いんきょかおう)」:過活動と消耗
若い年代は体力があると思われがちですが、無理な生活を続けると、体を潤す「陰液(いんえき)」が消耗し、「虚熱(きょねつ)」が生じることがあります。
- 陰虚火旺: 夜更かし、過度な活動、慢性的な睡眠不足、あるいは過労により、体の潤い成分が不足し、相対的に熱がこもりやすくなる状態です。比較的治りにくく、乾燥感を伴う口内炎が繰り返されることがあります。口の渇きや喉の痛み、寝汗なども伴うことがあります。
「まだ若いから大丈夫」と無理を重ねた結果、体の潤いが消耗し、内側から熱が生じているサインとも言えます。
徳永、私の若い頃のことを思い出しますと、これらすべてが当てはまるような気がします。なにか一つの原因というよりは、様々なことが関連しあって口内炎が出来ていたようです。
口内炎が出来にくくするために出来ること5選
それでは口内炎が出来にくくするためにはどうすればいいのでしょうか。今まで述べてきたことから総合的に出来る対策をお伝えします。
1. 免疫力を高める生活習慣
口内炎の最大の敵は、免疫力の低下です。体の中から健康にする意識が何よりも重要です。
- 質の良い睡眠をたっぷりとる: 睡眠は、体の修復と再生に不可欠です。毎日決まった時間に寝起きし、7〜8時間の睡眠を確保しましょう。寝る前にスマートフォンやPCを見るのを避け、リラックスできる環境を整えるのがおすすめです。
- ストレスを上手に解消する: ストレスは自律神経のバランスを崩し、免疫力を低下させます。趣味の時間を持つ、軽い運動をする、瞑想や深呼吸を取り入れるなど、自分に合ったストレス発散法を見つけましょう。溜め込まず、こまめに解消することが大切です。
- 適度な運動を習慣にする: ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、継続できる範囲で体を動かすことで、血行が促進され、免疫細胞が活性化します。ストレス解消にもつながり、一石二鳥です。
2. 粘膜を強くする食生活
口内炎は粘膜のトラブル。健康な粘膜を保つための栄養素を意識して摂りましょう。
- ビタミンB群を積極的に摂る: 特にビタミンB2とビタミンB6は、皮膚や粘膜の健康維持に欠かせません。レバー、納豆、卵、乳製品、緑黄色野菜、魚(特にカツオ、マグロ)などに豊富に含まれています。
- ビタミンCも忘れずに: 免疫力アップやコラーゲンの生成を助け、粘膜の健康をサポートします。柑橘類、イチゴ、キウイ、ブロッコリー、ピーマンなどに多く含まれます。
- 亜鉛を意識する: 細胞の再生や免疫機能に関わる重要なミネラルです。カキ、豚レバー、牛肉、ナッツ類、チーズなどに含まれます。
- バランスの取れた食事を基本に: 特定の栄養素だけを意識するのではなく、主食、主菜、副菜を揃え、多様な食材を摂ることが大切です。加工食品やジャンクフードばかりではなく、手作りの食事を心がけましょう。
- 体を冷やすものを控える(東洋医学的視点): 冷たい飲み物や生野菜の摂りすぎは、消化器系(脾胃)の働きを弱め、「湿(余分な水分や老廃物)」を溜め込みやすくします。温かい食事や飲み物を中心にし、体を冷やさない工夫をしましょう。
- 刺激物・甘いものを控える(東洋医学的視点): 辛いもの、脂っこいもの、甘いものの過剰摂取は、体内に「熱」や「湿熱」を生み出し、口内炎ができやすい状態を作ります。これらを控えめにすることが、体の中から口内炎を予防する対策になります。
- 特に前述の身体に熱がこもりやすい人(「心熱」「肝火」「胃熱」「脾胃湿熱」「陰虚火旺」):「熱」を冷ます食材: ゴーヤ、きゅうり、トマト、セロリ、緑豆、梨など。「湿」を取り除く食材: はと麦、小豆、冬瓜、きゅうり、枝豆など。「気」を巡らせる食材: セロリ、春菊、ミント、柑橘類など。「陰液」を補う食材: 黒豆、山芋、白きくらげ、枸杞(クコ)の実などでの食養生がおすすめです。
3. 口腔環境を清潔に保つ
口腔内の清潔は、口内炎の予防と悪化防止の基本です。
- 丁寧な歯磨き: 食後はもちろん、毎食後に丁寧に歯を磨き、食べかすやプラークを除去しましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシも活用するとより効果的です。
- うがい薬やマウスウォッシュの活用: 口腔内の細菌の繁殖を抑えるために、刺激の少ないうがい薬やマウスウォッシュを適宜利用するのも良いでしょう。ただし、アルコール含有量の多いものは粘膜を刺激することがあるので注意が必要です。
- 口腔内の乾燥を防ぐ: 口腔内が乾燥すると、粘膜が傷つきやすくなります。水をこまめに飲んだり、ガムを噛んで唾液の分泌を促したりするのも有効です。特に寝ている間は乾燥しやすいので、寝室の湿度を保つ工夫もしてみましょう。
4. 物理的な刺激から口を守る
思わぬ刺激で口内炎ができてしまうこともあります。
- 口の中を噛まない工夫: 食事中はよく噛み、早食いを避けることで、誤って頬や舌を噛んでしまうリスクを減らせます。
- 合わない歯科器具は相談を: 入れ歯や矯正器具が粘膜に当たって口内炎ができる場合は、歯科医に相談して調整してもらいましょう。
- 熱いもの・冷たいものに注意: 熱すぎる飲み物や食べ物、逆に冷たすぎるものも、粘膜にダメージを与えることがあります。適温で摂るようにしましょう。
5. 東洋医学的セルフケアを取り入れる
体質改善には、東洋医学の知恵が役立ちます。
- ツボ押し:
- 足三里(あしさんり): 膝のお皿の外側から指4本分下にあるツボ。胃腸の働きを整え、消化吸収能力を高めます。
- 合谷(ごうこく): 親指と人差し指の骨が交わる付け根のくぼみにあるツボ。体の気血の流れを整え、痛みや炎症を和らげる効果があります。
- 太衝(たいしょう): 足の甲、親指と人差し指の骨が合流する手前のくぼみにあるツボ。ストレスによる「肝の気」の滞りを解消し、イライラを鎮めるのに役立ちます。 これらのツボを、心地よいと感じる程度の強さで数秒間押し、ゆっくりと離すことを繰り返しましょう。
- 体を温める: 冷えは万病の元であり、消化器系の働きを弱めます。足湯や半身浴で体を温めたり、腹巻きをするなどして、内側から温めることを意識しましょう。
こきあ相談薬店で取り扱っております、ショウキ温灸器での温灸は「陽の気」を手軽に補え、胃腸を温めるだけでなく、心身を癒してくれる効果が抜群です。
最後に:繰り返しできる場合は専門家へ
これらの対策を続けても口内炎が頻繁にできる、または一つが長引く(2週間以上)、発熱やリンパ節の腫れなど全身症状を伴う場合は、自己判断せずに必ず医療機関(内科、口腔外科、または漢方医)を受診してください。背景に別の疾患が隠れている可能性も考えられます。
こきあ相談薬店が考える口内炎へのアプローチ
ここまでは西洋学的と東洋医学的視点から口内炎をどう考えるかをお伝えし、その対処法をお伝えしましたが、この章ではさらに、こきあ相談薬店では口内炎にどう向き合うかをお話します。
基本的な考え方はこれまで述べてきたとおりのことです。
口内炎は「炎」という字がついているように、体の中に起こっている炎症です。
そしてそれは、起こる原因が何にせよ、粘膜を「修復する力が不足」している、要は炎を消す力が不足していると考えます。
それでは、その粘膜を修復するにはどうすればよいのか?何が必要か??これが重要になってきます。
そしてその答えは、一言でいいますと、修復するための「栄養=血」が十分あり、きちんとそれが粘膜に届いているか?!これに尽きます。
それが出来るようになるためには、上記でお伝えした通りの規則正しい生活、質の良い睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動とストレス解消。(これらはいつも当店がお伝えしていることです。)これが基本になります。これはつまり、修復するための「血」の質と流れを整えるための基本のこととして、常日頃から心がけて欲しいことです。
これがきちんと出来てさえいれば、口内炎は出来にくくなりますし、できたとしても早く治ります。そもそも口内炎にすらなりにくいです。
これら基本のことを、ご自分で生活や食事に気を付け(=養生することで)毎日を過ごすことにより、整えることが出来るのが最も理想です。しかし、現代社会に生きていると、それがなかなか難しいのが現状です。
こきあ相談薬店では、栄養=血が不足していると考えられる方には鉄剤や棗製剤、高麗人参製品、巡りが悪いと考えられる方にはコエンザイムQ10製剤、生命力低下(=腎気不足)していると考えられる方にはすっぽんエキス製剤、体の新陳代謝を高める核酸製剤、などなど、お一人おひとりに応じた商品をご紹介し、栄養=血を増やし、質を良くし、よく巡らせることが出来るようになっていただくためのお手伝いをしています。
私と娘(徳永薬剤師)は何をしたか?!その経験談
ここで徳永薬剤師と私の話をまた持ち出します。
私が若かったころはまだ知識も全然なく、口内炎が出来たとしてもビタミン剤、よくても漢方薬を飲む程度のケアしかせず、なんとなくやり過ごしていました。
そのうちに東洋学的知識が深まったり、燕の巣エキス製剤に出会ったことにより、体の基本が整ったせいか、ほぼ口内炎とは無縁になりました。
徳永薬剤師の場合は、「血を増やす」棗製剤、「粘膜の修復を助ける」核酸製剤を常日頃から服用することにより、劇的に口内炎は出来なくなりました。
しかし、もともとの体質なのか、鉄不足に陥りやすいせいか、今現在でも、これらを飲むのを止めるとまた口内炎が出来てしまうようです。
もちろん、二人とも日ごろから規則正しい生活と十分な睡眠は心がけていますが、食事やストレス解消、運動などは、それぞれ、その時その時に柔軟に考えて取り掛かっています。
バランスのとれた食事、十分なストレス解消、適度な運動などを毎日完璧に行うには、現代社会で生きるうえで、あるいは家族を含む、集団生活の中ではなかなか難しいと私たちは考えています。また、かえってそれがストレスになる場合もあります。
これが、私たちが、柔軟に取り掛かっているという理由です。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします
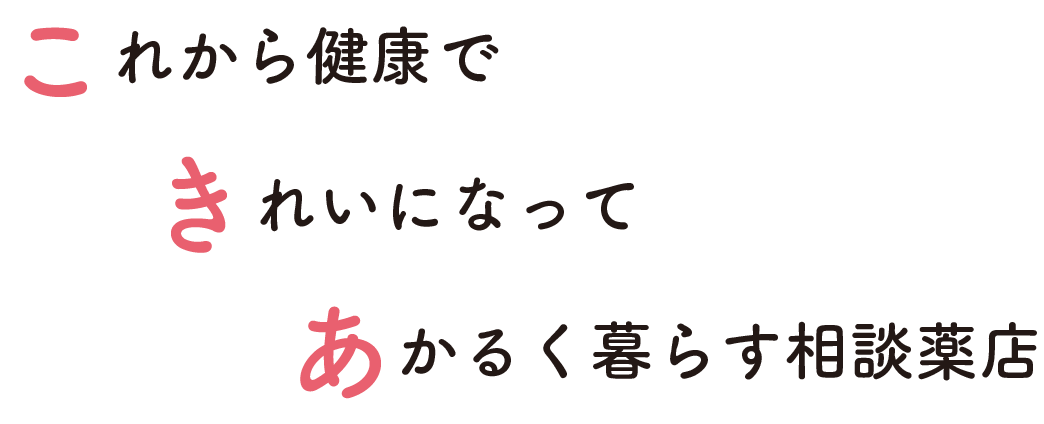

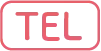 06-7897-7116
06-7897-7116