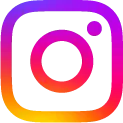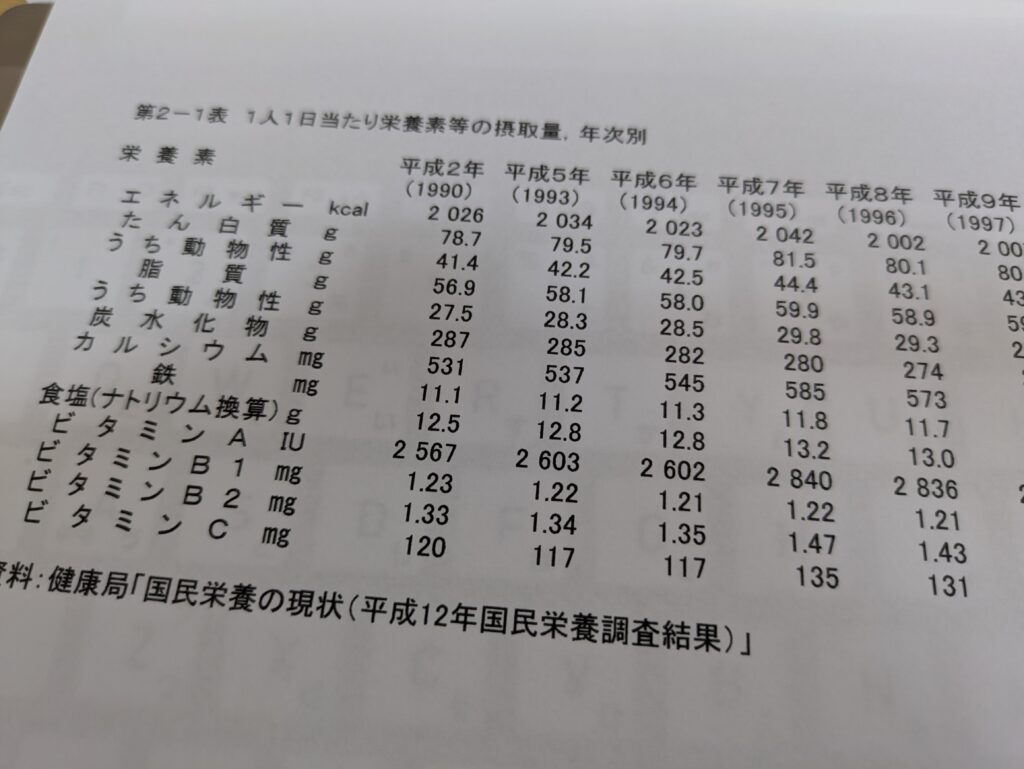少し前に「林修の今、知りたいでしょ!」というテレビ番組で「卵」についてやっていました。ご覧になられた方はありますか?
かつてはコレステロールを上げる悪者扱いされていた卵、今なお、店頭でも「卵は1日1個まででしょう?」とよく言われます。
ちなみに現在34歳の私の長男も、つい先日「俺は卵を1日1個以上食べたら罪悪感がある・・・おばあちゃんはずっと卵は1日1個以上食べたらあかんって言ってたから・・・」と言っており、このようなかつての情報が、いまだに若者にも幅を利かしているのかと思い知った訳であります。
本日のブログではそんな「卵」を食生活に取り入れるとどのような良いことがあるかを、テレビの内容を交えてお伝えしていきます。
このブログが少しでも皆様の健康増進にお役に立つことを願います。

目次
かつてコレステロールを上げる悪者扱いをされていた卵
かつては、卵に含まれるコレステロールが血中のコレステロール値を上げ、動脈硬化などの原因になると考えられていたため、「1日1個まで」と制限されることが多くありました。
私を含めこれを読んでおられる方も、そのように思われていた方が多いと思います。
卵がコレステロールの「悪者」とされるきっかけとなったのは、今から約100年以上前に行われた、ロシアでの動物実験が大きな要因です。
誤解の始まりとなった実験
- 時期: 1913年頃
- 場所: ロシア(当時のサンクトペテルブルク)
- 研究者: ニコライ・アニチコワ(Nikolai Anitschkow)ら
- 実験内容:
- 彼は、草食動物であるウサギに、卵黄や精製されたコレステロールを大量に含む高コレステロール食(動物性脂肪を多く含む食事)を与えました。
- 結果:
- ウサギの血中コレステロール値が急上昇し、血管にコレステロールが沈着して動脈硬化のような病変が引き起こされました。
なぜこれが誤解につながったのか?
この実験結果から、「食事からコレステロールを摂りすぎると、動脈硬化を引き起こす」という考えが強く支持されるようになり、コレステロールの摂取制限が世界的に広まる基礎となりました。
しかし、この実験には決定的な問題点がありました。それは、ウサギは本来コレステロールをほとんど含まない草を食べる草食動物であるという点です。
- ウサギ:コレステロールを分解・処理する能力が非常に低く、高コレステロール食を処理することができません。
- ヒト(雑食動物):ヒトは体内でコレステロールを合成し、また、食事からの摂取量に応じて体内の合成量を調整する機能(ホメオスタシス)を持っています。
つまり、草食動物であるウサギでの極端な実験結果を、雑食動物である人間にそのまま当てはめてしまったことが、「卵=悪」という長年の誤解を生む最大の原因となったのです。
しかし、その後の研究で以下のことがわかってきました。
- 食事由来のコレステロールの影響は小さい:
- 私たちの体内のコレステロールは、食事から摂る分よりも、肝臓で合成される分が大部分を占めています(約70〜80%)。
- 健康な人であれば、食事からコレステロールを多く摂っても、体が作る量を調整するため、血中のコレステロール値はそれほど上がらないことがわかってきました。
- 日本の食事摂取基準の変更:
- この知見に基づき、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、2015年版でコレステロールの摂取上限量が撤廃されました(※2020年版でも同様に上限は設けられていませんが、生活習慣病予防の観点から、飽和脂肪酸の過剰摂取を避けることが重要とされています)。
卵は「完全栄養食品」
実は卵は「完全栄養食品」とも言われるほど、良質なタンパク質(アミノ酸スコア100)、ビタミン類(ビタミンA, D, E, B群など)、ミネラル(鉄、亜鉛など)をバランス良く含む優れた食品です。
そりゃそうですよね。この卵から一つの生命が生まれてくるわけですから(有精卵の場合)、その命を育むためには十分な栄養が含まれているということは容易に想像できます。
ちなみに、有精卵であろうが無精卵であろうが栄養素的にはほぼ同じで、卵の価格の違いは餌や育て方のコストの違いによるものだそうです。
さらには卵の色の違いは鶏の種類の違い、黄身の色の違いは餌の色に影響され、たんぱく質やビタミンなどの栄養価は変わらないそうです。ただし、黄身の色味が濃いほどルテインやゼアキサンチンといった目の健康に良いとされるカロテノイドの含有量は多くなる傾向があるようです。
卵のたんぱく質は「アミノ酸スコア100」
卵が優れている最大の理由は、そのタンパク質の質にあります。
タンパク質は20種類のアミノ酸から構成され、そのうち9種類は体内で作れない「必須アミノ酸」として必ず食事から摂る必要があります。
- アミノ酸スコアは、食品に含まれる必須アミノ酸が、体が必要とする理想的なバランスにどの程度近いかを示す指標です。
- 卵のタンパク質は、この9種類の必須アミノ酸すべてが過不足なく、理想的なバランスで含まれているため、アミノ酸スコアは最高の100点となります。
これは、すなわち卵のタンパク質が消化吸収された後、私たちの体内で効率よく筋肉や細胞の材料として利用されることを意味します。
また、必須アミノ酸のうちとくに、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つはBCAA(分岐鎖アミノ酸)と呼ばれ、筋肉の構成とエネルギー代謝において非常に重要な役割を果たします
このBACCの1日に必要な最低量を卵3つほどで摂ることができます。
卵に含まれるコリンと脳の健康
卵には認知機能の維持や、将来的な認知症予防に役立つ可能性のある重要な栄養素が豊富に含まれており、近年、その効果が注目されています。
卵と認知症・脳の健康との関係において、特に重要な役割を果たすのが以下の2つの成分です。
1. コリン(Choline)と脳内伝達物質の関係
卵が脳の健康に良いとされる最も大きな理由が、卵黄に豊富に含まれるコリンです。卵は、すべての食品の中でもコリンの含有量が非常に高い食品です(特に卵黄)。
コリンとは神経伝達物質「アセチルコリン」の主要な原料となる成分です。
アセチルコリンとは、脳内で記憶、学習、認知機能に深く関わる神経伝達物質で、アルツハイマー型認知症では、このアセチルコリンが減少することが原因の一つと考えられています。コリンを補給することで、アセチルコリンの生成をサポートし、認知機能の低下を抑えることが期待されています。
コリンはリン脂質の一種であるレシチン(ホスファチジルコリン)の形で多く含まれています。卵に含まれるレシチンは、脳関門(脳に有害物質が入るのを防ぐ関所)を通過しやすい性質を持っているため、効率よく脳にコリンを届けることができると言われています。
アメリカではこのコリンの重要性が「ビタミンに近い物質」として認識されており、必須栄養素に指定されています。
男性では1日550mg、女性では1日425mg妊婦では1日450 mg、授乳婦では1日550 mgの積極的摂取をに推奨されています。(ちなみに現在の日本の「日本人の食事摂取基準」において、コリンの摂取基準はまだ設定されていません。)
一般的なMサイズの卵1個(約50g)に含まれるコリンは、約120〜150mg程度です。
アメリカの推奨量で見ると、成人女性(425mg)なら約3個、成人男性(550mg)なら約4個の卵を食べると、コリンの目安量を満たせる計算になります。
コリンは鶏のレバーには100gあたり290㎎、大豆には同じく116㎎、牛肉の赤身には90mg、豚ロースには74mg、魚の鱈には65mgなど、他の食材にも含まれています。
2. その他の脳に良い栄養素
卵はコリン以外にも、脳の健康維持に欠かせない栄養素を豊富に含んでいます。
- ビタミンB12
- 神経細胞の機能維持に必須であり、不足すると認知機能の低下につながるリスクが高まると言われています。
- コリンがアセチルコリンに変わる過程を助ける「サポーター」としての役割も果たします。
- タンパク質
- 良質なタンパク質は、脳の神経伝達物質や脳細胞そのものの材料になります。
- カロテノイド(ルテイン・ゼアキサンチン)
- 卵黄に含まれる黄色い色素成分で、強い抗酸化作用を持ちます。
- 近年の研究では、ルテインなどが脳に蓄積することで、認知機能の保護、特にアルツハイマー病の原因とされるアミロイドβ(ベータ)の凝集抑制や炎症の抑制に関与する可能性が示唆され、注目されています。
卵を摂取することは、単一の栄養素だけでなく、脳の健康維持に必要なコリン、ビタミンB12、良質なタンパク質、抗酸化成分を非常にバランス良く、効率的に補給できるという意味で、認知症予防に役立つ食品であると考えられています。
卵と血管の健康の関係
卵と血管の健康の関係は、最新の栄養学的な知見では、「適量の卵の摂取は心血管疾患(心臓病や脳卒中など)のリスクを上げることはなく、むしろ健康な食生活の一部として有益である」という見方が主流になっています。
前述のとおり、食事から摂取するコレステロール(食事性コレステロール)が血中のコレステロール値に与える影響は、以前考えられていたほど大きくないことが分かっています。血中コレステロールの大部分は、食事に関係なく肝臓で合成・調整されています。
また、多くの大規模な疫学研究のメタ解析(複数の研究を統合した分析)により、健康な人が1日1個程度の卵を摂取しても、心血管疾患(CVD)や脳卒中のリスクは上昇しないことが示されています。アジア人のコホート研究では、むしろリスクが低下する可能性を示唆する報告もあります。
以下のような研究結果もあります。
南オーストラリア大学(University of South Australia, UniSA)の研究結果
南オーストラリア大学(University of South Australia, UniSA)からは、卵と血管の健康、特にコレステロール値との関係について、従来の常識を覆す非常に重要な研究結果が発表されています。
南オーストラリア大学の研究結果のポイント
南オーストラリア大学のジョナサン・バックリー教授らの研究チームは、食事性コレステロールと飽和脂肪酸がLDL(悪玉)コレステロール値に与える影響を分離して調査するランダム化比較試験を行いました。
その結果、以下の点が明らかになりました。
- 悪玉コレステロールを上げる真の要因は飽和脂肪酸:悪玉コレステロール(LDLコレステロール)値の上昇の主要な原因は、卵に含まれる食事性コレステロールではなく、食事に含まれる飽和脂肪酸であると結論づけました。
- 「卵ではなく、ベーコンやソーセージ」:研究主任のバックリー教授は、「朝食の中で心臓の健康に悪影響を与える可能性が高いのは、卵ではなく、ベーコンやソーセージ(飽和脂肪酸を多く含む食品)なのだ」と述べています。卵はコレステロールは多いものの、飽和脂肪酸の含有量が少ないため、むしろLDLコレステロール値が低下する可能性が示されました。つまり、卵は心臓の健康に悪影響を与えないとして、卵の名誉回復を主張しています。
この研究の意義
この研究結果は、数十年にわたり「卵を食べすぎると心臓病のリスクが高まる」という根拠とされてきた、食事性コレステロールの影響に関する従来の偏見を覆す強力な科学的根拠となります。
健康な人にとって、卵を毎日適量(例えば1日1~2個)摂取することは、良質なタンパク質や認知症予防で述べたコリン、そして抗酸化作用のあるルテイン・ゼアキサンチンといった血管や脳に良い栄養素を効率よく補給できる、健康的な選択肢であると言えます。
卵に含まれる血管に良い成分
むしろ卵には、以下のような血管の健康をサポートする重要な栄養素が豊富に含まれています。
| 栄養素 | 血管の健康への働き |
| レシチン (ホスファチジルコリン) | ・血管壁に余分なコレステロールが沈着するのを防ぎ、血流をスムーズにする作用が期待されています。 |
| コリン | ・レシチンの一部であり、肝臓での脂質代謝をサポートし、脂肪肝の予防にも役立つ可能性があります。 |
| 良質なタンパク質 | ・血管を構成する細胞の材料となり、血管の弾力性や修復を助けます。 |
| ビタミンE | ・強い抗酸化作用を持ちます。動脈硬化は、LDL(悪玉)コレステロールが酸化して血管壁に沈着することで進行すると言われており、ビタミンEはこの酸化を防ぐ働きが期待されます。 |
| オメガ3脂肪酸 (飼料による) | ・鶏の餌によっては、血液をサラサラにする効果があるオメガ3脂肪酸(DHAやEPAなど)を卵に豊富に含むものもあります。 |
最大限に効率よく体に活かすための卵の食べ方は?
卵の栄養素を体内で効率よく吸収し、最大限に活かすためには、調理法や組み合わせにいくつかのポイントがあります。
特に、血管や脳の健康に良いとされるタンパク質、レシチン(ホスファチジルコリン)、ビタミン類の効率的な摂り方を解説します。
1. 「半熟」が最強の消化吸収率
タンパク質、皮膚のビタミンともいわれるビオチン、ビタミン類すべてにおいて、最も効率が良いとされるのが「半熟」の状態です。
| 目的の栄養素 | 最適な調理法 | 理由とポイント |
| タンパク質 | 半熟卵・温泉卵 | 生卵のタンパク質の吸収率が約50%なのに対し、加熱することで構造が変化し、消化酵素で分解しやすくなります。半熟状態(卵白が固まり、黄身がとろり)が、消化に最も負担をかけず、吸収率も高いとされています。(固ゆで卵は消化に時間がかかる傾向があります。) |
| ビオチン | 半熟〜固ゆで卵 | 生の卵白には「アビジン」というタンパク質が含まれており、これが黄身のビオチンの吸収を妨げます。アビジンは加熱することでその働きを失うため、白身に火を通した半熟以上の状態が効率的です。 |
| レシチン/コリン | 加熱調理した卵黄 | レシチンやコリンは、卵黄に豊富に含まれており、コリンは脳に吸収されやすい形態で含まれています。ビタミンB1やB6のように熱に弱い栄養素もありますが、半熟にすることで消化吸収が良くなり、結果的に効率よく利用されます。 |
2. 「油」と一緒に摂る:脂溶性ビタミンを逃さない
卵黄には、ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンが含まれています。これらは油と一緒に摂ることで吸収率が大幅に向上します。
- おすすめの調理法:
- 目玉焼き、オムレツ、スクランブルエッグ、卵焼き
- ポイント:
- 調理に使う油(オリーブオイルなど)と一緒に摂取することで、ビタミンAや抗酸化作用のあるビタミンEの吸収がアップします。
3. 「野菜」と一緒に摂る:不足を補い抗酸化力を高める
卵に不足している数少ない栄養素がビタミンCと食物繊維です。これらを一緒に摂ることで、栄養バランスが完璧に近づきます。
- おすすめの組み合わせ:
- オムレツやスクランブルエッグに、きのこやブロッコリーなどの野菜を加える。
- ゆで卵やポーチドエッグを、野菜たっぷりのサラダやスープにトッピングする。
- 効果:
- 食物繊維が腸内環境を整え、ビタミンCが卵にない栄養を補い、抗酸化作用を高めます。
4. 卵を食べるのに「最も効率的な時間帯」
- 朝食
- 卵の良質なタンパク質を朝に摂ることで、一日の活動に必要なエネルギーを作り出し、体を目覚めさせます。
- 朝食のタンパク質は、代謝アップや筋肉量維持にも効果的であるとされています。
- 卵黄に含まれるコリンは脳を活性化させるため、仕事や勉強の前の朝食に最適です。
卵は現代人のたんぱく質不足の救世主!
以上、卵の良い点について書いてまいりましたが、そもそも卵アレルギーがある方は卵は食べることはできません。
かくいう私自身も、アレルギーはありませんが、卵はいうほど好きではないので、積極的に食べる方ではありません。
前述の認知症予防に関しては卵は最低週に1個食べると、その予防効果が高まる。という結果が出ているそうです。
なにより、我々こきあ相談薬店では、食事に限らず、生活全般、あらゆることで、何事においても「ばっかり」はダメで、「ほどほど」「いい塩梅」「満遍なく」を最大のモットーとしておりますので、1日に卵を何個も何個も食べてください。ということはそれに反します。
とはいえ、現代人はたんぱく質を主として、必要な物がキチンと必要量、食事から摂れていないということがわかっていることも事実です。
特に、高齢者の方には、消化吸収が良く、他の食材と組み合わせて手軽に摂取できる卵は、積極的に食生活に取り入れていただきたいと思っています。
また、「朝タンパク質」が良いと言っても朝から手のひら分の牛肉の塊を食べてください!というのには、多くの方には無理があるような気がします。
やはり効率的に必要な栄養素を摂ろうと思えば「完全栄養食」の卵に頼るのが一番だと思います。
しかも、物価高で高くなったとはいえ、肉や魚に比べるとまだまだ安い!
私たちこきあ相談薬店では、たんぱく質不足を疑われる方には、卵を買ってきた時にひとパックを全部ゆで卵にしてストックしておいて、それを2,3日で食べきるようにしてください。とお伝えしています。(実際問題、それ以上置くとゆで卵は痛んでしまいます)
前述しましたが必須アミノ酸の内のBACCの最低必要量は卵3個でほぼ摂れますので、この食べ方でクリアできます。
かといって、これを食べきるために他のものが食べられなくなってしまうと本末転倒ですので、そこはお一人お一人が自分のお腹と相談しながら食べていただかないといけないのですが、卵は現代人のたんぱく質不足にはとても効率的な食べ物であることは間違いありません。
ちょっと小腹がすいたなぁ~と思ったときや、少しもの足りないなぁ~と思ったときに、その辺にある適当な物を食べるよりはゆで卵を食べる方が圧倒的に健康的です。
テレビ番組では「これからはラーメンを食べる時に味玉のトッピングは必須ですね~」とコメンテーターの方が言っておられました。」全くその通り!!だと思います。1つと言わず3つくらい頼んで欲しいくらいです。
毎食ごとに手のひらかげんこつ分のたんぱく質を
タンパク質が不足するとなぜ良くないのか?!は以前にブログに書きましたのでそちらをご覧いただけたらと思います。
たんぱく質は体に貯めておけないので、毎食ごとに指を除けた手のひらか、げんこつ分(人により違いますが、調理前の肉や魚の重量で約80g~160g程度)を摂取する必要があるといわれています。
みなさまは摂れていますか?
私は「意識しないと食べられない」のが実際です。
そんな時にお世話になるのが、本日延々と書いてまいりましたこの「卵」です。
あまり好きではない卵でしたが、知ればしるほど有難くいただけるようになってきました(;^_^A
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
ご相談は全国どこからでも、ZOOM、ライン電話、ライン動画、お電話、メールなどで承ります。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/ でご連絡お待ちしております。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
全国どこからでも、ZOOM、公式ライン、お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/ でご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします
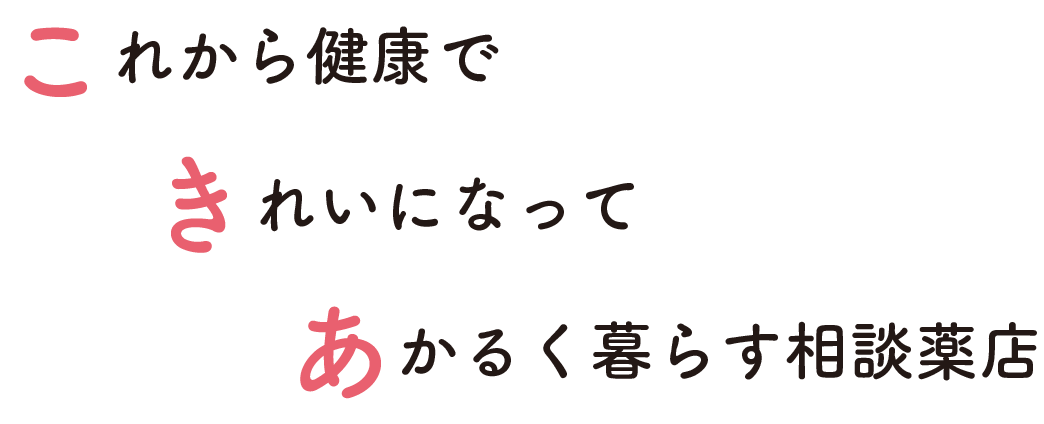

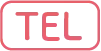 06-7897-7116
06-7897-7116