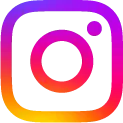数か月ほど前、糖尿病専門薬剤師をされている大学の先輩の講演会があったので参加してきました。
本日のブログは、40数年ぶりの先輩との再会話・・・は横に置いておいて、その時に印象に残った話を交えながら、糖尿病について、とくに身の回りに多くおられるⅡ型糖尿病についてのお話をしたいと思います。
このブログがご自身が糖尿病、あるいはご家族や周りの方が糖尿病で悩んでおられる方のお役に立つことを願っています。

目次
糖尿病の現在
厚生労働省が3年ごとに行っている「患者調査」の令和5年(2023年)の調査によると、
- 糖尿病で現在治療を受けている患者総数は 552万3,000人 (男性 317万7,000人、女性 234万6,000人)
令和4年(2022年)の「国民健康・栄養調査」(「国民健康・栄養調査」は、健康診断の結果などから推計される数字で、治療を受けていない人も含めた、より広範な「糖尿病有病者」と「予備群」の状況を示します。)によると、
- 「糖尿病が強く疑われる者」は約1,000万人
- 「糖尿病の可能性を否定できない者(予備群)」も約1,000万人
つまり、日本の成人のおよそ6人に1人は、糖尿病であるか、その予備群であるという状況が続いています。
日本人に糖尿病が多いと考えられる理由
日本において糖尿病患者が多いとされる背景には、複数の要因が複合的に絡み合っていると考えられています。主な要因を以下に挙げます。
1. 遺伝的素因(日本人に特有の体質)
- インスリン分泌能の低さ: 日本人を含むアジア人は、欧米人に比べてインスリンを分泌する能力が遺伝的に低い傾向があると言われています。これは、もともと農耕民族として、インスリンを大量に必要とするような高カロリー食を摂る機会が少なかった歴史的背景に関係しているとも言われています。 このため、たとえ欧米人と同じ量のカロリーを摂取したり、同じ程度の肥満になったとしても、インスリン分泌が追いつかず、より糖尿病を発症しやすい体質であると考えられています
- 「倹約遺伝子」説: 人類は過去の飢餓に耐えるため、少ないエネルギーで効率よく脂肪を蓄える遺伝子を持っている、という説があります。これは、アメリカの遺伝学者ジェームズ・ニールが1962年に提唱したものです。
現代の飽食の時代では、この遺伝子が逆に糖尿病のリスクを高める要因になっている可能性が指摘されています。
2. 食生活の変化(欧米化と飽食)
- 高カロリー・高脂肪食の増加: 戦後の高度経済成長期以降、日本人の食生活は急速に欧米化しました。肉類や揚げ物、加工食品、菓子パン、清涼飲料水などの摂取が増え、総カロリーや脂質の摂取量が増加しました。
- 炭水化物(糖質)の過剰摂取: 伝統的な和食も炭水化物が中心ですが、現代の食生活では、精製された炭水化物(白米、パン、麺類)の摂取量が増え、さらに間食や夜食の習慣も増えています。
- 不規則な食生活: 朝食を抜く、夕食が遅い、早食いなどの不規則な食習慣も、血糖値の急激な上昇や肥満につながりやすくなります。
- 遺伝的にインスリン分泌能力が低い日本人が、このようなインスリンに大きな負担をかけるような食生活や下記の運動不足に直面したことで、膵臓のインスリン分泌細胞が疲弊し、糖尿病の発症や進行につながりやすくなったと考えられます。
3. 運動不足
- 身体活動量の低下: 交通機関の発達やIT化、デスクワークの増加などにより、日常生活における身体活動量が大幅に減少しました。歩く機会が減り、座っている時間が長くなったことが、肥満の増加やインスリン抵抗性の悪化につながっています。
- 運動習慣の欠如: 忙しい現代生活の中で、意識的に運動する時間を確保することが難しいと感じる人が少なくありません。
4. 肥満の増加
- 上記の食生活の変化と運動不足が複合的に作用し、肥満、特に内臓脂肪型肥満が増加しています。
- 内臓脂肪が増えると、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じ、血糖値が上がやすくなります。日本人は欧米人よりも軽度の肥満でも糖尿病を発症しやすい傾向があります。
5. ストレス
- 現代社会は、仕事や人間関係、経済状況など、多様なストレスに満ちています。
- ストレスは、血糖値を上昇させるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促したり、食生活や運動習慣の乱れ(やけ食い、アルコール摂取増など)につながったりすることで、糖尿病のリスクを高めると考えられています。
6. 高齢化
- 糖尿病は加齢とともに発症リスクが高まる病気です。日本の高齢化は急速に進んでおり、それに伴い糖尿病患者数も増加しています。
- 高齢になると、基礎代謝が低下したり、筋肉量が減少したりすることで、若い頃と同じ生活をしていても血糖値が上がりやすくなります。
これらの要因が複雑に絡み合い、日本における糖尿病患者数の増加につながっていると考えられます。特に、遺伝的な背景と現代の生活習慣のミスマッチが、日本人における糖尿病の大きな原因であると言えるでしょう。
「食生活の欧米化」だけを挙げても、欧米人の方が肥満の割合が高いにも関わらず、日本人も同等、あるいはそれ以上に糖尿病患者数が増加しているのは、遺伝的素因が強く関係しているとしか考えられません。
遺伝的背景が「土台」となっている: 遺伝的素因という「土台」の上に、現代の生活習慣という「積み重ね」が加わることで、糖尿病という「建物」がより強固に築かれてしまった、というイメージです。どちらか片方だけでは、ここまでの患者数の増加は説明が難しいでしょう。
もちろん、高齢化やストレスなども重要な要因ですが、「インスリン分泌能の低さ」という日本人に特徴的な遺伝的背景と、それに追いつかない「現代の生活習慣の急激な変化」という社会的な背景が組み合わさった点が、日本の糖尿病患者数増加の最も根本的かつ大きな理由であると広く認識されています。
糖尿病の診断
糖尿病の診断は、主に血液検査で行われます。いくつかの異なる検査項目と基準値があり、それらを総合的に判断して診断が下されます。
糖尿病診断の主な基準
以下のいずれかに該当する場合、糖尿病と診断されます。
- HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)値が6.5%以上
- HbA1cは、過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖の状態を示す指標です。赤血球の中にあるヘモグロビンというタンパク質に糖が結合したもので、血糖値が高いほど多く結合します。
- 日常の食事や運動の影響を受けにくく、過去の血糖コントロールを反映するため、診断や治療効果の判定に広く用いられます。
- 空腹時血糖値が126mg/dL以上
- 検査前10時間以上、食事を摂らない状態で測定した血糖値です。
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)で2時間値が200mg/dL以上
- 空腹時に75gのブドウ糖を溶かした水を飲み、その後の血糖値の変化を調べます。通常、飲む前(0分)、30分後、60分後、120分後の血糖値を測定します。
- 特に2時間後の血糖値が重要視されます。
- 随時血糖値が200mg/dL以上
- 食事時間に関係なく、任意の時間で測定した血糖値です。
- この場合、同時に糖尿病の典型的な症状(口の渇き、多飲、多尿、体重減少など)があることが診断の条件となります。
診断のポイントと流れ
- 上記の基準のうち、HbA1cまたは空腹時血糖値、OGTTのいずれかが基準値を超えた場合、別の日にもう一度検査を行い、同じように基準値を超えることが原則として必要です。これは、一度の検査だけでは一時的な血糖値の上昇である可能性も考慮するためです。
- ただし、HbA1cが6.5%以上かつ空腹時血糖値が126mg/dL以上のように、複数の項目が同時に基準値を超えている場合や、典型的な糖尿病症状があり、随時血糖値が200mg/dL以上の場合は、一度の検査で糖尿病と診断されることがあります。
- また、過去に糖尿病と診断されたことがある人も、糖尿病と診断されます。
糖尿病予備群(境界型)の診断
上記の診断基準には満たないものの、血糖値が高めの状態を糖尿病予備群(境界型糖尿病、耐糖能異常などとも呼ばれます)と診断されることがあります。
- HbA1c値が6.0%~6.4%
- 空腹時血糖値が110mg/dL~125mg/dL
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)で2時間値が140mg/dL~199mg/dL
予備群の段階で生活習慣の改善に取り組むことで、糖尿病への進行を食い止めたり、発症を遅らせたりすることが可能です。
糖尿病になると起こる様々なこと
糖尿病と診断されると、日常生活や健康においてさまざまなことが起こり得ます。最も大きな問題は、血糖値が高い状態が続くことで、全身の血管や神経が徐々にダメージを受け、最終的に重篤な合併症を引き起こすことです。
1. 日常生活への影響
- 食事制限と管理: 食事内容に常に気を配る必要があり、好きなものを自由に食べられないストレスを感じることがあります。外食や会食時もメニュー選びに悩むことが増えるでしょう。
- 運動習慣の必要性: 定期的な運動が推奨されるため、時間の確保や習慣化に努力が必要です。
- 血糖測定と薬の管理: 毎日決まった時間に血糖値を測ったり、薬を服用したり、インスリン注射が必要な場合は自己注射を行ったりと、自己管理の負担が増えます。
- 通院の負担: 定期的な診察や検査のための通院が必要になり、時間や交通費の負担が生じます。
- 精神的ストレス: 病気になったことへのショック、将来への不安、食事制限や自己管理のプレッシャーなどから、精神的なストレスを感じやすくなります。
2. 合併症による身体的な影響
糖尿病の最大の影響は、高血糖状態が続くことで引き起こされる以下のような三大合併症と、その他の全身性の合併症です。これらは自覚症状がないまま進行することが多く、発見が遅れると深刻な事態になりかねません。
2-1. 糖尿病の三大合併症
- 糖尿病網膜症(失明のリスク)
- 目の奥にある網膜の血管がダメージを受け、出血したり詰まったりします。
- 初期には自覚症状がほとんどなく、進行すると視力低下や飛蚊症が現れ、最終的には失明に至る可能性があります。
- 定期的な眼科検診が不可欠です。
- 糖尿病腎症(透析のリスク)
- 腎臓の小さな血管が傷つき、老廃物をろ過する機能が低下します。
- 初期は無症状ですが、進行するとむくみ、貧血、倦怠感などが現れ、末期には腎臓が機能しなくなり、人工透析が必要になります。透析導入の原因で最も多いのが糖尿病腎症です。
- 週に複数回の透析治療は、生活の質(QOL)を大きく低下させます。
- 糖尿病神経障害(しびれ、痛み、足病変のリスク)
- 全身の神経がダメージを受け、特に足の感覚神経に異常が出やすくなります。
- 手足のしびれ、痛み、感覚の麻痺(特に足裏)が現れます。足の感覚が鈍くなるため、小さな傷やヤケドに気づきにくくなり、それが悪化して潰瘍や壊疽につながり、最悪の場合足の切断に至ることもあります(糖尿病性足病変)。
- 自律神経にも影響が出ると、立ちくらみ、便秘・下痢、発汗異常、ED(勃起不全)などの症状が現れることもあります。
2-2. その他の全身性の合併症
- 動脈硬化の促進: 脳梗塞、心筋梗塞など、命に関わる心血管疾患のリスクが非常に高まります。
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血): 脳の血管が詰まったり破れたりすることで、半身麻痺や言語障害などの後遺症が残ることがあります。
- 心筋梗塞・狭心症: 心臓を栄養する血管(冠動脈)が詰まったり狭くなったりして、胸の痛みや呼吸困難を引き起こします。
- 免疫力の低下: 感染症にかかりやすく、治りにくくなります(膀胱炎、肺炎、歯周病など)。
- 骨粗しょう症: 骨がもろくなり、骨折しやすくなるリスクも指摘されています。
- 認知症のリスク上昇: 糖尿病はアルツハイマー型認知症や血管性認知症のリスクを高めると言われています。
3. 社会的・経済的な不都合
- 医療費の増加: 定期的な通院、検査、薬代、もし合併症が進行すれば手術や透析治療など、医療費の負担が大きくなります。
- 仕事への影響: 重篤な合併症に至ると、仕事の継続が困難になったり、転職を余儀なくされたりするケースもあります。
- 生命保険や医療保険: 新規加入が難しくなったり、保険料が高くなったりする場合があります。
このように、糖尿病は単に血糖値が高いというだけでなく、放置すると全身に深刻な影響を及ぼし、日常生活の質を著しく低下させる可能性がある病気です。だからこそ、早期発見と適切な管理、そして継続的な治療が非常に重要になります。
病気の中で唯一患者さんが医療者に謝っている病気
糖尿病という病気が、しばしば患者さん自身の生活習慣(食事や運動など)に起因すると見なされがちであり、その結果、患者さんが「自分のせいで病気になった」「管理ができていないから血糖値が高い」といった自責の念や罪悪感を抱きやすいという、非常にデリケートな側面があります。
なぜ患者さんが「謝って」しまうのか?
- 生活習慣病という認識: 糖尿病、特に2型糖尿病は生活習慣との関連が深いため、「自己管理ができていない」というレッテルを貼られやすい傾向があります。医療者からの指導も、時に患者さんにとっては「できていないこと」を指摘されているように感じられることがあります。
- 社会的な偏見: 糖尿病に対する社会的な誤解や偏見も、患者さんの心理的負担を増大させます。「贅沢病」「自己管理不足」といった誤った認識が、患者さんを追い詰めることがあります。
- 治療の難しさ: 糖尿病の治療は、薬を飲むだけでなく、毎日の食事管理や運動、血糖測定など、患者さん自身の努力が大きく求められます。生活習慣を変えることは容易ではなく、思うように血糖値が改善しない場合に、患者さんが自分を責めてしまうことがあります。
- 医療者側のコミュニケーション: 医療者側にも、患者さんの背景や感情に配慮しない一方的な指導になってしまうケースが皆無ではありません。患者さんの努力を認め、寄り添う姿勢が不足していると、患者さんは孤立感や罪悪感を深めてしまいます。
この事実から考えるべきこと
糖尿病は、遺伝的要因、年齢、ストレス、社会的環境など、患者さん個人の努力だけではコントロールしきれない多くの要因が絡み合って発症・進行する複雑な病気であるにもかかわらず、実際には「食べ過ぎ」「運動不足」という一面で語られてしまう事が多いように思えます。
診察や投薬の時に「血糖値が高いですね~」と医師や薬剤師に言われよううものならば、「すみません💦つい甘い物を食べてしまいました」「ごめんなさい💦💦暑くて運動はできませんでした。」などとつい答えざるを得ない心理的圧迫を受けてしまう方もおられるでしょう。
そして病院の外に出た時には、そんな言葉を口にしてしまったばかりに、知らず知らずのうちに「なんで私は甘いものが我慢できないんだろう・・・」「僕ってなんて駄目な奴だ・・・」という自己肯定感が駄々下がりの状態になってしまいます。
本来、謝る必要など全くないことであるにも関わらず謝り、そのことにより下げなくてもいい自己肯定感まで下がってしまう・・・という悪循環。こんなことで心身に良い影響があるわけはありません。
思いもよらない出来事が起こり食事内容を気にするどころではなかった・・・、転職してストレスマックスなひと月だった・・・このようなことがあったかもしれない患者さん一人一人の背景にまで思い至らない医療者側の未熟さが、この一因にあることもあります。
「今回数値が悪かったのは、何かあったの?」まず、医療者側から、この一言を問われると、「実は・・・」患者さんの答えは変わってくるはずです。
患者さんと医療者が同じ目線で信頼関係を築けた時から、本当の糖尿病の治療ができるように思います。
もちろん医療現場でこのような声掛けを受けておられる方もあると思いますが、講演では現状では、それが出来ているところはまだまだ少ないということでした。
もちろん、このような患者さんばかりではなく、単に自分の欲望をコントロールできない人にはそれなりの指導が必要になることもあると思われます。
こきあ相談薬店に糖尿病の方が来られたら・・・
一番に理解していただきたいのは、やはり合併症の怖さです。
日々の血糖値コントロールも大切ですが、まず、目、神経、腎臓の働きが悪くなっていないかを定期的に検査をされるべきだと思っています。
これらは1度悪くなると不可逆、つまり良くなることはありません。いかに悪くなることを食い止めるか。これが最重要になります。
- 目の場合は、糖尿病患者さんの約15%が糖尿病網膜症にかかっていると推定され、年間約3,000人がこの病気で失明しています。
- 腎臓病では、本透析医学会が毎年発表している「わが国の慢性透析療法の現況」の2022年末の調査によると、2022年に新たに人工透析を始めた患者さん(新規導入患者数)は、 39,683人でした。このうち、最も多い原因疾患は「糖尿病性腎症」で、全体の39.5%を占めています。
- このことから、単純計算すると、年間約15,675人(39,683人 × 0.395)が糖尿病性腎症を原因として新たに人工透析を始めることになります。
- また、糖尿病による足切断は、糖尿病の最も重篤で悲しい合併症の一つです。これは「糖尿病性足病変」と呼ばれる一連の足のトラブルが進行した結果として起こります。足にできた小さな傷が「治りにくい潰瘍」となり、さらに細菌感染が加わって「壊疽」へと悪化します。壊疽が進行し、命に関わるような重篤な感染症(敗血症など)のリスクが高まったり、周囲の健康な組織にまで壊死が広がるのを防ぐために、やむを得ず足の切断が選択されることになります。
- 日本透析医学会のデータによると、糖尿病性腎症が原因で人工透析を導入する患者さんのうち、透析患者全体の約3.7%が下肢切断を経験しているという報告もあります(2014年のデータ)。
- 年間で正確な足切断の人数を把握するのは難しいですが、糖尿病患者の下肢切断頻度は、非糖尿病患者の7.4倍から41.3倍にも上るとされています。これは、糖尿病がいかに足の健康に大きな影響を与えるかを示しています。
脅すようですが、血糖値が高いだけでは体は痛くもなんともない、つまり、自覚症状がありませんので、このようなことが起こりうるという事実を頭に入れていただくことが第一番になります。
糖尿病の人が甘い物を欲するのには訳がある
糖尿病の方は血糖を細胞内に取り入れるのを助けるホルモンであるインスリンの量が不足しているか、インスリンが効きにくくなっている(インスリン抵抗性)状態です。この場合、血液中のブドウ糖が細胞内にうまく取り込まれないため、細胞はエネルギー不足になります。
結果として細胞がブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなり、体全体が「エネルギーが足りない」と感じるため、疲労感や倦怠感といった症状が現れやすくなります。
ブドウ糖が利用できないと、体は代わりに脂肪や筋肉を分解してエネルギーを得ようとします。これにより、体重減少が起こったり、倦怠感がさらに増したりすることもあります。
また、体は効率の良いエネルギー源であるブドウ糖を求めて、炭水化物や甘いものを欲するように信号を送ることがあります。特に2型糖尿病の方で顕著な場合がありますが、インスリンの働きが悪いと、炭水化物や甘いものを摂取した際に血糖値が急激に上昇します。すると、体は血糖値を下げようと大量のインスリンを分泌します。この大量のインスリンによって、今度は血糖値が急激に下がりすぎることがあります(血糖値スパイクによる低血糖状態に近い感覚)。 この急激な血糖値の低下は、脳に「エネルギーが足りない!」という強い信号を送り、再び炭水化物や甘いものを欲するサイクルを生み出します。この繰り返しが、あたかも薬物依存のように甘いものや炭水化物への欲求を強めてしまう「糖質依存」につながると考えられています。
さらに、糖尿病の食事療法は、我慢を伴うことが多く、それがストレスになることがあります。ストレスを感じると、人は手軽に快感を得られる甘いものに手を出しやすくなる傾向があります。甘いものを食べると、脳内では「ドーパミン」という快感物質が分泌されます。これにより、一時的に幸福感や満足感が得られます。しかし、この快感は一時的なもので、すぐに「もっと欲しい」という欲求につながりやすくなります。糖尿病で血糖コントロールが難しい状態にあると、この報酬系が過敏になり、さらに甘いものを求める傾向が強まることがあります。
このように、糖尿病の人が炭水化物や甘いものを欲するのは、体の生理的な反応と脳の心理的な反応が複合的に作用しているためです。
ご家族の方が糖尿病の場合、口にされるお菓子や甘いものに過敏になられることがあると思いますが、実は、糖尿病の方の体内は深刻なエネルギー不足に陥っていることをまず、理解されることが大切です。
糖質への欲求はどうコントロールすればよいのか?
1. 血糖値の安定化を最優先にする
糖質への強い欲求は、血糖値の乱高下が大きく影響しています。まずは血糖値をできるだけ安定させることが、食欲コントロールの第一歩です。
- 規則正しい食事: 決まった時間に食事を摂り、長時間空腹にならないようにしましょう。空腹時間が長すぎると、次の食事で血糖値が急上昇しやすくなります。
- 低GI食品の選択: 糖質の吸収が穏やかな低GI(グリセミックインデックス)食品を選びましょう。玄米、全粒粉パン、そば、野菜、きのこ類などがこれにあたります。これらは血糖値の急激な上昇を抑え、その後の急降下も防ぎます。
- 食物繊維を積極的に摂る: 食物繊維は糖の吸収を緩やかにする効果があります。野菜、海藻、きのこ、こんにゃくなどを毎食取り入れましょう。
- 食べる順番を工夫する: 食事の最初に野菜やきのこ、海藻など食物繊維が豊富なものを摂り、次にタンパク質(肉、魚、卵、豆腐など)、最後に炭水化物という順番で食べると、血糖値の急上昇を抑えられます。
2. 食事内容の質を高める
「我慢」だけでは長続きしません。満足感のある食事を心がけましょう。
- 良質なタンパク質と脂質を摂る: タンパク質や良質な脂質は、血糖値に影響を与えにくく、満腹感を持続させる効果があります。肉、魚、卵、大豆製品、アボカド、ナッツ類などをバランス良く取り入れましょう。
- 間食の見直し: どうしても間食がしたくなったら、血糖値が上がりにくいものを選びましょう。ナッツ、チーズ、無糖ヨーグルト、ゆで卵、野菜スティックなどがおすすめです。ただし、量には注意が必要です。
- 味覚のリセット: 人工甘味料などに頼りすぎず、素材本来の味を活かした薄味に慣れることで、甘みへの依存を減らすことができます。
3. メンタルと行動の対策
食欲は心理的な要因も大きく関わっています。
- ストレス管理: ストレスを感じると、甘いものに手が伸びやすくなります。運動、趣味、リラックスできる時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
- 十分な睡眠: 睡眠不足は血糖コントロールを悪化させ、食欲を増進させるホルモンにも影響を与えます。質の良い睡眠を心がけましょう。
- 代替行動を見つける: 甘いものが欲しくなったら、すぐに口にするのではなく、別の行動に置き換える練習をします。例えば、散歩に出かける、温かいお茶を飲む、歯磨きをする、趣味に没頭するなどです。
- 記録をつける: 自分がどんな時に甘いものを欲するのか、何を食べたのかを記録することで、自分の傾向を把握しやすくなります。
現代社会では身近に手軽に食べられるものとして、菓子パンや砂糖を使った甘いお菓子などがあふれかえっています。空腹時間が長すぎるのはよくないといって、間食にそのような物を食べてしまうのは、いくら3度の食事に気を配っていても、元の木阿弥です。
もちろん!絶対に食べてはいけない!!といっているのではありません。あくまでも嗜好品、人生を楽しむためのとっておきとして楽しまれるのが良いと思います。
血糖値が安定してくると、自然と甘いものはあまり欲さなくなります。そうなるまではすこし頑張って血糖値を安定させるための努力は必要になるかと思います。
私が血糖値の急上昇を防ぐために実践している方法
私は糖尿病ではありませんが、帰宅後、おなかがペコペコな時は、血糖値の急上昇を防ぐために、(行儀はあまりよくないですが)お炊事をしながら、まず、納豆を食べています。納豆がない時はチーズであったり、冷ややっこであったり、前日の残りの煮物であったり・・・とにかくつい手軽に口にしがちなクッキーやチョコレートは食べません。
関西ではこのように、小腹が減った時にちょっと何かを食べる事、物を「虫おさえ」といいますが、この虫おさえを少し食べることによって、いざ食卓に座り「いただきます」と同時に、目の前のお茶碗のご飯にがっつくことはなくなります。
そして食事はまず、おかずから食べる。次にご飯を食べる。この順番で食べています。(世間一般的には野菜→メインのおかず→ご飯といいますね)
気を付けていただきたいことは、脳のエネルギー源はブドウ糖のみです。ですので脳を守るためにも、毎食必ず子供のお茶碗1杯程度の糖質は摂るようにしてください。(糖質換算では最低1日で約130gほどが脳には必要)
血糖値スパイクについては下記のブログに詳しく書いています。よろしければこちらもご覧になってください。
口にするもの、食事の時のちょっとした工夫で血糖値の急上昇は防げます。
糖尿病の方は知らず知らずのうちに食事に対してもストレスを溜めておられることがあります。
食事は毎日のことですので、身体に対する影響も重大ですが、それがストレスになってしまっては元も子もありません。
工夫をしながら食生活を楽しんでいただきたいです。
こきあ相談薬店では今までお話してきたような生活養生、食養生のアドバイスとともに、血糖値スパイクを抑えるための食品、漢方食品、お茶などをご紹介しています。
まず、今の自分の体の状態がどうなのか。これをきちんと把握された上で、次に、自分がどうなりたいのか、どうしたいのかを決められ、血糖のコントロールや、体へのダメージを最小限にすることに取り掛かられると、常にのしかかっているストレスも減少するのではないでしょうか。
根本から治していくために
こきあ相談薬店ではお越しいただいた際に、お客様の生活スタイルや食事の摂り方などを詳しくお聞きし、それぞれお一人お一人に適した漢方薬、漢方食品、サプリメントなどをご提案すると同時に、その方に合った生活や食事の養生法をお伝えしています。
体調というものは一度正のスパイラルに入ると、どんどん良くなっていくものです。今現在、負のスパイラルに陥っているものを、正のスパイラルにもっていくことをサポートするのが我々がおすすめする物とアドバイスである思っていただければよいです。
これらを決め、始められるのはあくまでもお客様ご本人です。こきあ相談薬店が出来ることはそれを後方支援することです。
こきあ相談薬店へは下記の方法でご連絡いただけます。ご予約は公式ラインからご連絡いただくのが確実です。
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
このブログはこきあ相談薬店の薬剤師 芳田がお届けしました。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

✿❀こきあ相談薬店の基本情報❀✿
住所:〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1丁目25-15
電話番号:06-7897-7116
FAX番号:06-7897-7116
メールアドレス:kochia.yakuten@gmail.com
営業時間:月・火・木・金→9:30~18:30
土→9:30~13:30
水・日・祝→お休み
ホームページ:

Google:

ブログ:

✿❀ご相談のご予約方法✿❀
お電話(06-7897-7116)、メール(kochia.yakuten@gmail.com)、公式ライン、ホームページのお問い合わせ欄https://kochia-yakuten.com/contact/で承ります。
お気軽にご連絡ください。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokia.yakuten?igsh=MWx3cmp4YnA4ejk2MQ%3D%3D&utm_source=qr

公式ライン https://lin.ee/8ukzuc4

✿❀オンラインショップもございます✿❀

全国発送いたします
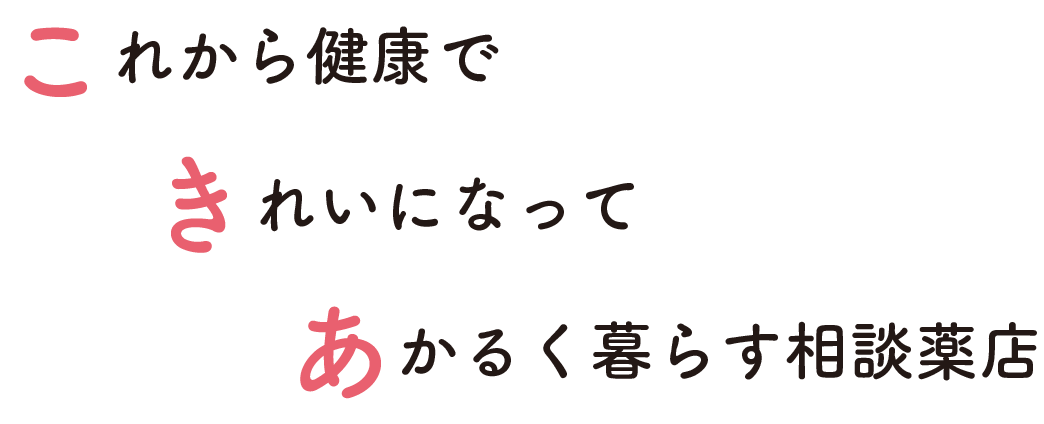

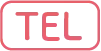 06-7897-7116
06-7897-7116